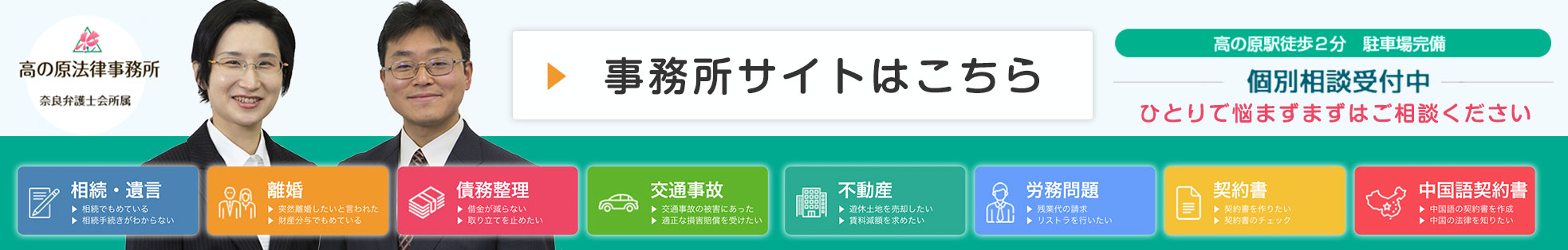コラム
成年被後見人の相続で遺産の使い込みが成年後見人によるものだと発覚した場合の解決手段や回避方法を解説
相続で使い込みが成年後見人によるものだと発覚したときは、相続人は成年後見人に対して不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。成年後見人による使い込みを防止するには、任意後見制度、後見監督人の選任、後見制度支援信託などが有効です。
相続時の使い込みが成年後見人によるものだった時の解決手段や回避方法を解説します。
成年被後見人の相続で使い込みが成年後見人によるものだと発覚した場合の対処方法と予防策とは?
成年被後見人が亡くなった後で相続手続きや遺産分割を行ったところ、遺産や相続財産が予想以上に少なくなっており、使い込みが成年後見人によるものだと発覚することがあります。
遺産相続の際、使い込みが成年後見人によるものだったときは、相続人から不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
ただ、被害額の回復を図ることは容易ではありません。
そのため、使い込みを予防、回避するための様々な施策を講じておくことが大切です。
使い込みが成年後見人によるものだったケースの対処方法と予防策について詳しく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や精神的な障害により、判断能力を失ってしまった方に代わり、成年後見人が財産管理や契約行為を行う制度です。
成年後見制度は、大きく分けると2種類に分類できます。
成年後見制度と任意後見制度
成年後見制度(法定後見制度)は、既に認知症や精神的な障害により、判断能力を失った方がいる場合に、本人や関係者が家庭裁判所に申立てを行い、裁判官が成年後見が必要な状態にあることを確認した上で、適切な人を成年後見人として選任する制度です。
成年後見人となる人は、本人や家族が選べるわけではなく、家庭裁判所の裁判官が選ぶ点に特徴があります。
任意後見制度は、認知症や精神的な障害になる前に本人が後見人になってほしい人といざという時に後見人になってほしい旨の契約を交わしておきます。そして、後見人が必要な状態になった時は、その後見人が就任しますが、その際に後見人を監督する立場の人として任意後見監督人が家庭裁判所により選任されます。
後見人になってほしい人を選ぶことができますが、その代わり、後見人の監督をする任意後見監督人が家庭裁判所に選ばれるという制度です。
成年後見人に使い込まれることはあり得るのか?
法定後見制度では、成年後見人は、当事者の状況を考慮したうえで裁判官が選任します。
家族による使い込みが懸念されるケースでは、家族以外の第三者として弁護士や司法書士が成年後見人に選任されることが多いでしょう。
もちろん、経済的に弁護士や司法書士に報酬を支払うことが難しい場合には、家族が選ばれることもあります。
また、成年後見人を監督する役目の人として成年後見監督人が選ばれることもあります。
そして、成年後見人になった人は、家庭裁判所又は成年後見監督人による監督の下で、成年被後見人の財産管理を行います。
財産管理の状況については、家庭裁判所へ報告する義務があります。
初回は必須とされており、次のような書類を作成して提出します。
- 後見等事務報告書
- 財産目録
- 収支予定表
その後は、年に1回、自主的に後見等事務の報告を行うこととされています。これを定期報告と言います。
こうした書類を正確に記載していれば、使い込みは防げるはずですが、成年後見人が書類等を偽造してしまえば、成年被後見人の財産を横領したり着服することも可能です。
そのため、成年後見人が使い込みをすることが大きな問題になっています。
成年被後見人の相続において使い込みが発覚することもある
成年後見人は、成年被後見人の財産管理に関して幅広い権限を有しているだけに、成年被後見人の家族などでさえ、その内容を把握しにくいものです。
そのために、成年被後見人が亡くなった際の相続の時に、成年被後見人の財産が相当に少なくなっており、成年後見人が使い込みをしていたことが発覚するケースもあります。
使い込みをしやすいケースとは?
使い込みをしやすいのは、成年被後見人の親族が成年後見人になっているケースです。
その親族が成年後見人の子どもなどの法定相続人であれば、いずれ自分が相続するのだからと、財産管理がいい加減になりがちで、自分のために使ってしまうことがあります。
たとえ、成年後見人が親族でも家庭裁判所に定期報告する義務があります。
そのため、定期報告で不審な点があれば、その時点で使い込みが疑われるはずですが、様々な書類を偽造してしまえば、成年被後見人が亡くなるまで使い込みが発覚しないこともあります。
また、弁護士、司法書士などの第三者が成年後見人になったとしても、安心できるわけではありません。
定期報告は自主的に行うものとされていることもあり、書類の偽造も容易です。
特に、成年被後見人の家族が財産管理について無関心で、成年後見人にまかせっきりの場合は、使い込みされやすいと言えます。
そのため、第三者が成年後見人に就任している場合でも、成年被後見人の家族がその財産管理状況について、成年後見人に定期的に報告を求めるなど、成年後見人にコンタクトを取り続けることが重要です。
成年被後見人の相続において使い込みが発覚した時の対処方法
成年被後見人の遺産分割や相続において、使い込みが成年後見人によるものだと発覚した場合、成年被後見人の相続人がどう対処すべきか、まとめます。
成年後見人がいくら使い込みしたのか金額を調査する
成年被後見人が亡くなった際に、遺産が残っていなかったというだけでは、成年後見人の使い込みが原因なのかどうかはっきりしません。まずは、何にどれだけ使っていたのかをはっきりさせる必要があります。
家庭裁判所に成年後見人が提出する後見等事務報告書等は、本人の家族に見せなければならない法的根拠がないことから、成年被後見人の相続人の手元にその記録がないこともあります。
そのため、まず、家庭裁判所に報告書の閲覧・謄写申請を行う必要があります。
家庭裁判所から報告書を入手したら、不審な点がないか確認します。
生活費、医療費、介護費用などが中心ですが、その費用が水増しされていないか、成年被後見人のためにならない支出に使われていないかといったことを確認します。
矛盾点が発覚した場合は、その数字を積み重ねて、使途不明金の総額を算出します。
成年後見人に使途不明金の使い道を追及する
使途不明金の総額がはっきりしたら、成年後見人に対して使い道を追及します。
使い込みを成年後見人が認めれば、その金額の返還を求めます。
具体的には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行います。
なお、不当利得返還請求は、不当利得返還請求ができることを知った時から5年、または、不当利得返還請求ができる時から10年で消滅時効にかかってしまうので注意してください。
不法行為に基づく損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅時効になります。
ただ、成年後見人が使い込みしたことを認めない場合は、訴訟を提起しなければならないこともあります。
訴訟になった時は、成年後見人が使い込んだ証拠が必要です。
家庭裁判所に提出した報告書の不自然な点だけでなく、報告書が偽造されていたことや成年被後見人のために使われていなかったといったことを立証しなければなりません。
成年後見人の刑事告訴も検討する
成年後見人が使い込みした場合は業務上横領に該当します。
横領とは、自己の占有する他人の物を横領する行為ですが、成年後見人は職務で成年被後見人の財産を管理しており、その財産を横領していることから、「業務上横領」という重い刑罰の対象になります。
法定刑は十年以下の拘禁刑です。
業務上横領は、弁護士や司法書士といった専門家が成年後見人に就任していた場合だけでなく、子どもや親族が成年後見人となっている場合でも成立します。
なお、業務上横領は、刑法255条により、親族間の犯罪については刑を免除したり、告訴がなければ提起できないといった特例が設けられています。
ただ、成年後見の業務は公的性格があるので、成年後見人は成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っています。
そのため、成年後見人が成年被後見人と親族関係にある場合でも刑法255条により、刑法上の処罰を免除することができませんし、量刑の判断で親族関係を酌むべき事情として考慮することもできないというのが最高裁の考え方です(最決平成24年10月9日 刑集 第66巻10号981頁)。
弁護士が使い込みした場合の依頼者見舞金制度
弁護士が職務上、成年後見人として使い込みをしていた場合は、日本弁護士連合会の依頼者見舞金制度を利用することも検討しましょう。
この制度は、依頼者が弁護士の業務上の横領によって財産を失った場合に弁護士会に申請することで、弁護士会から500万円を限度に支給を受けられる制度です。
使い込みを防止するには?
成年被後見人の相続において、使い込みが成年後見人によるものだと発覚した場合は、上記のような手段を講じることで、相続人は使い込みした金額を成年後見人から取り戻すことも可能です。
ただ、親族の場合はもちろん、弁護士や司法書士といった専門家が使い込みをしたケースでも、すでに何らかの用途に費消してしまい、返金や損害賠償金の支払いが難しいことも少なくありません。
そのため、成年後見制度の利用を検討する際に、使い込みを防止するための措置を講じておくべきです。
その方法について解説します。
成年後見監督人を選任してもらう
後見開始の審判を申し立てたときは、成年後見人を家庭裁判所が選任しますが、成年後見監督人を必要に応じて、選任できることになっています。
成年後見監督人とは、成年後見人が適切に後見事務を行っているか監督する立場の人です。
成年後見監督人がいれば、成年後見人は報告書の偽造や使い込みをしづらい状況になります。
成年後見監督人には、弁護士などの専門家が選任されることが多く、月々の報酬が発生しますが、多額の財産がある場合は、成年後見監督人の選任を求めて使い込みを防止しましょう。
任意後見制度の利用を検討する
成年後見制度(法定後見制度)ではなく、任意後見制度なら使い込みを予防するのに有効です。
任意後見制度ならば、本人が信頼できる人を選ぶことができます。
さらに、任意後見を開始するときは、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されることになっています。
任意後見監督人の役割は任意後見人の後見事務を監督することなので、任意後見人による使い込みのリスクは少なくなります。
後見制度支援信託を利用する
成年被後見人が莫大な財産を有している場合は、成年後見人に使い込みされることを心配する方が多いものです。
そんな時は、日常的な支払いに必要な分だけ、成年後見人に管理してもらい、それ以外の財産は信託銀行などに預けておく方法もあります。
後見制度支援信託という制度です。
後見制度支援信託を利用すれば、日常的な支払をするのに必要十分な預貯金等のみを成年後見人の管理にゆだねて、残りの財産は信託銀行等に信託することで成年被後見人の財産を保護することができます。
信託銀行等に信託する預金のことを支援預貯金口座(後見制度支援預貯金)と言いますが、すべての預金をいったん支援預貯金口座に預けて、生活費等の必要な金額のみを定期的に成年後見人が管理する普通預金口座に振り込む形で利用することもできます。
また、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約するときは、家庭裁判所が発行する指示書が必要になるため、成年後見人が使い込むことは難しくなります。
家族信託を利用する
財産管理のみが目的なら成年後見制度ではなく、家族信託の利用も選択肢の一つです。
家族信託は、家族や親族などに自分の財産の管理を信託できる制度で、成年後見制度や任意後見制度の代わりに利用できます。
成年後見制度や任意後見制度においては、後見人や後見監督人が選任されますが、弁護士や司法書士等の専門家の場合は、一定額の報酬の支払いが必要です。
家族信託では信託する相手が家族や親族なので、高額な報酬は必ずしも必要ありません。
また、家族信託は遺言書とは別の方法で、資産を承継させる人を決められることから、事業承継や資産承継対策としても活用が広がっています。
なお、家族信託の場合、財産を管理するのは家族や親族です。
最終的には、信託した家族や親族にその財産を承継させることが想定されていますが、使い込みを防止したい場合は、信託監督人を選任して使い道を監督させることも検討します。
まとめ
成年後見制度は、認知症や精神的な障害により本人が判断能力を失った場合に、本人に代わって成年後見人が財産を管理し、保護するための制度です。
それでも、成年後見人が使い込みをすることが発覚することもあります。
特に、成年被後見人となった本人が亡くなった後の相続でこうした使い込みが発覚した場合は、財産の返還を求めることが難しいこともあります。
そのため、成年後見人が使い込みをすることを予防するための様々な施策を講じておくことが大切です。
相続時に使い込みが発覚し、成年後見人によるものであることが判明するなどの成年被後見人の遺産を巡るトラブルが生じているときは、弁護士にご相談ください。