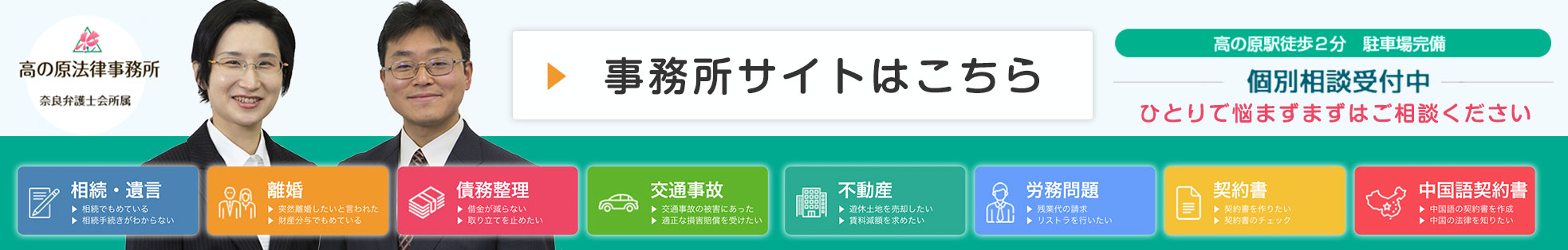コラム
相続人が不明なときの対処法|行方不明の人がいる際の遺産分割協議を弁護士が解説!
相続人の一部が行方不明で遺産分割が進まない場合、どうすればよいかを弁護士が詳しく解説します。戸籍の調査方法、不在者財産管理人の選任、失踪宣告などの手続きをわかりやすく説明し、相続人が不明でも相続を進めるための具体的な対応策を紹介します。
相続の手続きを進めたいのに、推定される相続人の一部が行方不明で困ってしまう方は少なくありません。
連絡がとれないままでは遺産分割協議が進まず、不動産の名義変更や預金の引き出しもできない状態です。
放置すれば、相続税の申告や財産の管理にも支障が出てしまいます。
この記事では、相続人が不明なときの手続き方法を弁護士がわかりやすく解説します。
今どの手続きが必要か、どの制度を利用すればよいかが整理でき、無駄なトラブルを防げるでしょう。
相続人が不明でも、正しい手順を踏めば相続を進めることは可能です。
相続人が不明だと遺産分割協議が進まない
遺産分割協議は、相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意を得るための大切な手続きです。
法律上、相続人の一人でも欠けた状態では有効な協議とは認められず、協議書を作成しても法的な効力を持ちません。
つまり、相続人が不明なままでは遺産の処理が進まないのです。
相続手続きには期限があり、放置しておくと以下のような問題が生じるかもしれません。
- 不動産の名義変更ができず売却や担保設定が不可能になる
- 預貯金の引き出しや相続税申告が進められない
- 他の相続人との間で不信感や争いが生まれる
遺産分割協議は、家族関係の整理と権利の確定を行う場でもあります。
誰がどの財産を取得するのかを明確にすることで、将来のトラブルを防げます。
相続人全員が平等な立場で参加し、合意を得ることが法律上の原則であり、協議の成立こそが相続完了への第一歩なのです。
法定相続人が行方不明の場合
法定相続人が行方不明の場合、ひとまず連絡をとれないかを確認します。
ただし、連絡先や住所すらわからないという場合は下記の手順で進めましょう。
- 戸籍謄本を調べる
- 手紙で連絡をする
それぞれ解説します。
戸籍謄本を調べる
相続人の中に連絡できない人がいる場合、まず行うべきは戸籍謄本の調査です。
行方不明者であっても、生存している限り相続権は失われません。
したがって、その所在を可能な限り特定し、遺産分割協議の案内を行う必要があります。
戸籍謄本をたどることで、現在の本籍地や居住地の手がかりを得られます。
手続きの流れとしては次のとおりです。
- 被相続人の戸籍を出生から死亡まで取得し、相続人を確定
- 不明な相続人については戸籍の附票を請求し、住所を確認
- 現住所が不明な場合は、市区町村への照会や住民票消除の記録を確認
戸籍附票には転居履歴が記載されているため、現住所の特定に役立ちます。
調査の過程で住所が判明すれば、次の段階として連絡を試みることが重要です。
専門家に依頼すれば、戸籍取得の代行や調査の手続きをスムーズに進めることも可能です。
手紙で連絡をする
行方不明の相続人の住所がわかったら、できるだけ丁寧に連絡をとりましょう。
手紙で相続の発生と協議の必要性を伝えるのが一般的です。
連絡先を明記して電話や面談での説明を促すのが望ましいです。
ほかの相続人だけで決めた内容を承認させようとする手紙は避けるべきで、慎重な姿勢が信頼を得る第一歩となります。
話し合いが進まない場合は、弁護士など第三者を通して連絡をとる方法も検討しましょう。
法定相続人がまったく不明な場合の手続き
上記の手順を踏んでも連絡がとれないなど、法定相続人が完全にわからないケースでは、連絡のあてすらないため、遺産分割協議を行うには「不在者財産管理人の選任」か「失踪宣告」の手続きが必要です。
それぞれの手続きと、どちらを選択すべきかの判断基準について解説します。
不在者財産管理人の選任
相続人が行方不明で、相続の手続きが進められないとき、不在者財産管理人の選任制度が活用されます。
これは、不在者がまだ生きている可能性を前提に、その人に代わって財産の管理者を裁判所が認めるものです。
不在者財産管理人には、弁護士などの法律の専門家や、不在者と利害関係のない第三者が選ばれます。
家庭裁判所が適任と判断した人物を選任し、不在者の財産を公平かつ適切に管理します。
不在者財産管理人の選任の申立先は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。
利害関係を持つ相続人・配偶者・債権者等が申立人となります。
申立時には
- 不在者の戸籍謄本
- 附票
- 不在を証する資料
- 財産目録
- 管理人候補者の住民票など
を提出する必要があります。
管理人が選任されると、まず不在者の財産調査と目録作成を行い、定期的な報告を裁判所へ提出しなければなりません。
ただし、遺産分割協議に参加したり不動産売却を行ったりするためには、別途「権限外行為許可」の申請が必要です。
管理人の報酬や職務は、不在者が現れたり失踪宣告がなされたりするまで継続します。
権限外行為許可とは
権限外行為許可は、不在者財産管理人が通常の管理を超える行為について、家庭裁判所の許可を得る制度です。
不在者の不動産を売却したり、遺産分割協議に参加したりする場合が該当します。
権限外行為許可を得るには、不在者財産管理人が家庭裁判所に「権限外行為許可申立書」の提出が必要です。
申立書には、行為の目的や理由、不在者に与える影響などを具体的に記載し、必要に応じて財産目録や契約書の写しなどの資料を添付します。
家庭裁判所は内容を審査し、不在者の利益を害さないと判断した場合にのみ許可を出します。
失踪宣告
失踪宣告とは、行方不明者の生死が一定期間明らかでない場合に、法律上その人を「死亡したものとみなす」制度です。
通常、普通失踪では生死不明が7年間継続したとき、特別失踪(事故・災害等で危難に遭遇した場合)では、危難が去った後1年間見つからないときに申立が認められます(民法第30条・第31条)。
失踪宣告が確定すれば、その人は失踪期間満了日の時点で死亡したものとみなされ、婚姻関係は解消され、相続が開始します。
その結果、行方不明者は相続人から除かれ、代襲相続人がいる場合はその人が遺産分割に参加します。
代襲相続人とは、本来の相続人が死亡や相続欠格などで相続できない場合に、その人に代わって相続権を引き継ぐ人のことです。
たとえば、被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代襲相続人として相続します。
失踪宣告後に不在者の生存が確認された場合には取消しが可能で、その取消しによってすでに行われた分割などに調整が必要なこともあります
不在者財産管理人の選任か失踪宣告の判断基準
どちらの制度を選ぶかは、主に不在者の行方不明期間と、生存の可能性・手続きを急ぐ必要性などで判断します。
まず、失踪宣告を申し立てるには、普通失踪なら7年間、危難失踪なら1年間の無事確認できない期間が必要です。
その期間を満たしていないときは、失踪宣告は認められず、不在者財産管理人の選任となります。
また、相続税の申告期限(死亡後10か月以内)を考慮すると、長期間待つ失踪宣告よりも、比較的早く制度を利用できる不在者財産管理人の方を優先することが多いです。
一方、すでに長期間にわたって行方不明で、もはや生存が困難と考えられるようなケースでは、失踪宣告方向への申立を検討します。
ただし、家族感情や将来発見されるリスクも念頭に置き、司法判断や専門家の意見を仰ぐことが望ましいです。
相続人が不明でも相続可能なケース
ここまでは相続人が不明なケースでの対処法について解説してきましたが、相続人が不明の状態でも例外的に相続できるケースがあります。
具体的には次の2パターンです。
- 遺言書がある
- 法定相続分かつ共有名義で相続登記する
それぞれ解説します。
遺言書がある
相続人が不明な場合でも、遺言書が存在すれば相続手続きを進められるケースがあります。
遺言書には、財産をどのように分けるかが明確に示されており、法定相続人の確定が難しいときでも、遺言に基づいて遺産の承継を行えます。
家庭裁判所の検認を経た公正証書遺言であれば、内容の真正性が担保され、遺産分割協議を行う必要もありません。
遺言書が有効な場合、手続きは次のように進みます。
- 遺言執行者が指定されていれば、その人が相続登記を実施
- 不明な相続人がいても、遺言書に記載された受遺者に所有権移転
- 相続税申告も遺言の内容を基に算出
法定相続分かつ共有名義で相続登記する
法定相続分に基づく共有名義で相続登記を行う方法もあります。
この手続きを行うことで、遺産分割協議を待たずに不動産の名義を相続人全員名義に変更できます。
相続人が行方不明の場合、その人の法定相続分も含めて共有登記を行う形です。
具体的には、
- 判明している相続人の分のみ登記申請を行う
- 不明者の持分部分には「持分登記」を残しておく
- 不在者財産管理人が選任された後、その人を通じて残りの手続きを進める
この方法により、急を要する固定資産税や管理義務などの対応を先に整えられます。
不在者の持分を確保したまま登記ができ、法的安定性も高いです。
ただし、相続人全員が揃うまでの一時的な措置でしかなく、売却などの処分はできません。
相続人が不明な場合に弁護士に相談するメリット
相続人が不明な場合、なるべく早期に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
具体的なメリットは次の3つです。
- ケースにあった対処法をアドバイスしてもらえる
- 相続人の調査を専門的に代行してもらえる
- 法的手続きをスムーズに進められる
それぞれ解説します。
ケースにあった対処法をアドバイスしてもらえる
相続人が不明なケースでは、状況によりとるべき手続きが大きく異なります。
「相続人が行方不明の場合」と「相続関係自体が複雑な場合」では進め方が変わります。
弁護士は、事実関係を整理し、最も適切な方法を具体的に提案可能です。
一般的な流れとしては、
- 相続人の範囲を確認
- 戸籍や附票から居所を調査
- 不在者財産管理人の申立ての要否を判断
などを段階的に検討します。
独自判断で進めると無効な協議書を作ってしまうおそれがあり、時間や費用が余計にかかるかもしれません。
弁護士であれば、個別の事情を踏まえた助言ができ、スムーズな相続ができるようになります。
相続人の調査を専門的に代行してもらえる
相続人の不明者について、戸籍や附票をたどって関係を確認する作業は非常に手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、法的手続きに則った形で正確な調査を代行してもらえるため、時間を大幅に節約できます。
戸籍の収集や本籍地の確認、住所履歴の調査などを一つひとつ自分で行うのは大変です。
弁護士であれば、漏れのないように進め、すべての相続人を特定することが可能です。
結果として、誤りのない相続関係図を早期に作成でき、後から「相続人の確認が不十分だった」といった問題を避けられます。
法的手続きをスムーズに進められる
相続人が不明な場合、法的な手続きは複雑になりがちです。
弁護士に依頼すれば、家庭裁判所への申立てや書類作成など、実務的な手続きを代わりに進めてもらえます。
行方不明者がいる場合、「不在者財産管理人の選任」を申立て、代理人を通じて遺産分割協議を行う方法がとられます。
こうした手続きは、提出書類や添付証明が多く、一般の方が独自に対応するのは難しいです。
弁護士が関与することで、必要な書類を正確に整え、申立てから協議成立までを一貫して進められます。
複雑な事務作業や法的判断を任せられることで、精神的な負担も軽くなり、確実に手続きを完了できる点が大きな利点です。
まとめ
この記事では、相続人が不明な際に行うべき手続きや、弁護士に相談するメリットについて解説してきました。
主なポイントは以下のとおりです。
- 戸籍調査や附票確認で相続人を特定する
- 不在者財産管理人や失踪宣告を活用できる
- 弁護士に依頼すれば正確かつ迅速に進められる
相続人が不明でも、正しい手順を踏めば遺産分割を進めることは可能です。
相続手続きは、法律と時間の制約がある中で冷静に進めることが重要です。
弁護士に相談することで、状況に応じた最善の対応策を提案してもらえます。
最近では、初回相談が無料の法律事務所も多くあります。
一人で悩まず、まずは専門家に相談して解決までのサポートを受けられないか検討してみましょう。