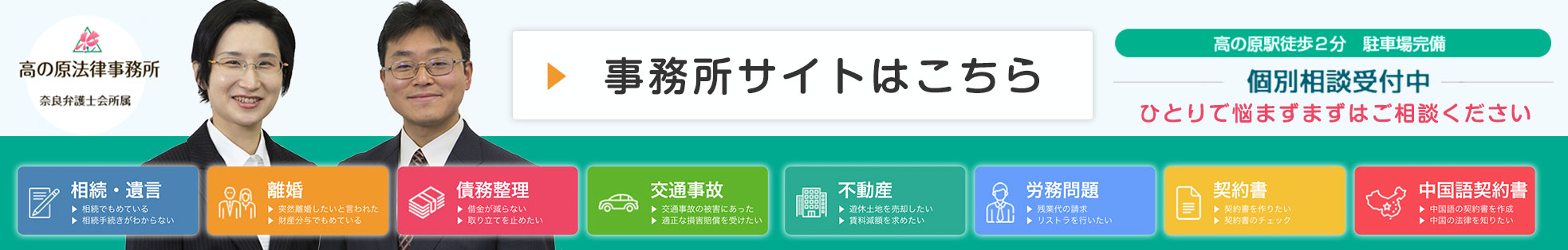コラム
相続において使途不明金や使い込みがある場合の遺産分割や解決方法を解説
相続の際の使途不明金については、遺産相続の前に弁護士に依頼して預金の使い込みをした相続人にその金額の返還を求める必要があります。使途不明金の解決策についてケースごとに解説します。
相続の際の使途不明金の発生原因と解決策、使い込みの取り戻し方を解説
相続開始前後に使途不明金が発覚した場合は、使い込みによって減ってしまった相続財産を元に遺産分割協議を行うことになりかねません。
このような場合は、使途不明金が発生した原因を突き止めて、使い込みをした相続人にその額の返還を求めたり、使い込みの分は持ち戻したうえで、使い込みをした相続人の法定相続分を減らす形で遺産分割を行うことを検討すべきです。
しかし、実際に使途不明金が発覚すると相続人同士で争いになってしまい、冷静な話し合いが難しくなることもあります。このような場合は、弁護士に相談して解決策を探ることが大切です。
相続の際の使途不明金とは
相続開始の時点で被相続人が有していた遺産を分け合うのが遺産分割です。
ところが遺産分割前にこの遺産の一部を他の相続人が使い込んでいることもあります。
例えば、親が亡くなったケースでは、親と同居する等、親の身近にいた子どもが親の預貯金通帳を管理していて、勝手に使っていることもあります。
このような場合、本来あるはずの遺産総額よりも少なくなってしまいます。
このように、本来あったはずの額より遺産が少なくなっている分について、どのような対応すべきかというのが、相続の際の使途不明金の問題です。
相続の際の使途不明金は取り戻せる?
相続において使途不明金が発生した場合は、遺産を使い込んだとみられる法定相続人に、その相当額を遺産に戻すように求めることになります。
実際には、遺産を返還してもらえないことも多いため、使い込んだ分を持ち戻して遺産分割する形で対応します。つまり、使い込みをした相続人はその額に相当する遺産を既にもらったものとして、残りの遺産分割では、取り分が少なくなるという扱いです。
使い込みした額が多額に上り、遺産がほとんどない状態の場合は、他の相続人は使い込みをした相続人に、それぞれの法定相続分に相当する金額の返還を求める形になります。
家庭裁判所の遺産分割調停では使途不明金を取り戻せない
遺産分割で揉めていたり、相続人だけでは協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停と審判を利用することになります。
ただ、遺産分割調停や審判は、現存している遺産をどのように分け合うか話し合う手続きです。
使途不明金となってしまった遺産は、遺産分割調停で取り戻すことはできません。
もちろん、遺産を引き出していた相続人が使い込みを認めた場合は、使い込んだ分を持ち戻して遺産分割する形で調停や審判をすることが可能です。
それに対して、遺産がほぼ無くなっていて、使途不明金を取り戻す必要がある場合は、使途不明金相当額の返還を求める訴えを簡易裁判所もしくは地方裁判所に提起する必要があります。
具体的には、不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得の返還請求を求める旨の民事訴訟を提起する形になります。
使途不明金が発生する5つの原因
使途不明金が発生するのは次の5つのケースです。
- 被相続人のために相続人が引き出していたケース
- 被相続人の承諾により相続人が引き出していたケース
- 相続人が勝手に無断で引き出していたケース
- 被相続人が自分で預金を引き出していたケース
- 相続人が預金口座の凍結に備えて引き出していたケース
それぞれどのような扱いになるのか確認しましょう。
被相続人のために相続人が引き出していたケース
被相続人が要介護状態だったり、入院している場合は、自分でATMなどから預金を出金することができません。
そのため、同居している子どもや主に介護を担っている子どもに預金通帳やキャッシュカードを預けて、介護費や医療費の支払いに充ててもらっているケースもあります。
介護費や医療費は明細が発行されるので、その明細と引き出した金額が合っていれば使途がはっきりするので問題ありません。
でも、被相続人が使う日用品の購入などでは、レシートを取っておいたり、帳簿を付けていることは少ないので、本当に日用品の購入に使ったのか?使ったとして何に使ったのか明確でないこともあります。
このように明細が残っていない引き出し額は、使途不明金となるので、トラブルの原因になってしまいます。
この場合、被相続人の預金から引き出した相続人とそれ以外の相続人はどのように対処したらよいのでしょうか?
被相続人の預金から引き出した相続人は、その金銭が被相続人のために使ったことを説明できるように明細や記録を残しておくことが重要です。
介護費や医療費の明細を保管することはもちろんですが、日用品の購入に充てた分もレシートを取っておいたり、家計簿などを付けておくことが望ましいでしょう。
それ以外の相続人の立場ならば、使途不明金となっている額については、裁判を起こして返還を求める必要があります。
そのためには、預金通帳と明細などを突き合わせて、具体的な額を計算する必要があるので、やはり、介護費や医療費の明細を取り寄せる必要があります。
被相続人の承諾により相続人が引き出していたケース
被相続人の生前にその承諾を得て相続人が引き出すケースとしては、介護を主に担っている子どもへの謝礼などという名目で多めに出すことを被相続人が容認していたことも考えられます。
この場合は、介護の謝礼という名目だったとしても、法的にはその相続人への生前贈与の性質を帯びるのが一般的です。
その他の相続人側の対応としては、使途不明金に相当する金額が生前贈与に当たるとして、民法903条の特別受益を主張することが考えられます。
また、使途不明金の額が法定相続分をはるかに上回る場合は、遺留分を侵害しているものとして、民法1046条に基づいて、遺留分侵害額の請求を行うことが考えられます。
相続人が勝手に無断で引き出していたケース
被相続人の預金通帳やキャッシュカードを預かっている相続人が、勝手に引き出していたケースです。
その使途や用途がはっきりしないケースでは使途不明金になるため、民事訴訟を提起するなどして返還を求めることになります。
使途不明金相当額の返還を求めるには次のような対応が必要です。
- 金融機関から取引履歴を取り寄せて、被相続人名義の預金口座から引き出された日時、金額などを調査し、特定する。
- その引き出しの日時の後で使い込みをした相続人名義の預金口座等に同額の入金がなされていたか確認する。
その他、預金通帳やキャッシュカードを被相続人が管理できる状態にあったのか、自分でATMや銀行窓口に出金に赴ける状態だったのかといったことも争点になります。
被相続人が自分で預金を引き出していたケース
亡くなる直前まで、被相続人の判断能力が衰えておらず、自力でATMや銀行窓口に出金に赴ける状態だった場合は、被相続人自身が生前に引き出していることもあります。
被相続人が自分で預金を引き出して、自分のためにお金を使う分には何の問題もないわけですが、その金額が多すぎる場合は、同居している相続人が使い込んでいたという疑いを掛けられて、使途不明金問題が生じることもあります。
そのため、同居中の相続人としては、被相続人に家計簿を作ってもらい、お金をしっかり管理してもらうべきです。
自分で財産の管理をするのが難しいケースでは、被相続人が多額の引き出しをしたのを察した際に、何に使うのか聞いて、そのメモや記録を残しておくといった予防策を講じることが考えられます。
また、兄弟などの他の法定相続人にも、被相続人がお金を使っているといった話を共有しておくことも有効です。
相続人が預金口座の凍結に備えて引き出していたケース
被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせた場合は、金融機関が銀行口座を凍結します。
凍結された後は、原則として預金の引き出しができなくなるため、凍結に備えてあらかじめ、多額の金銭を引き出しておくこともあります。
被相続人が亡くなった後は、病院や介護の費用の清算、葬式の費用などで多額の資金が必要になります。
いくらかかるか分からないため、余分に引き出しているケースも珍しくないでしょう。
相続人全員がその点を了承していれば問題ありませんが、同居している一部の相続人が勝手に引き出していたケースでは、使途不明金問題に発展してしまうこともあります。
使途不明金問題を予防するためには、
- 預金口座の凍結に備えて預金を引き出した事実を相続人全員で共有しておく。
- 病院や介護の費用や葬式の費用の明細をとっておき、支払った金額を明確にする。
- 余った金額は金庫などに保管して遺産分割できるようにする。
といった対応が必要です。
使途不明金がある場合の対処の流れ
使途不明金がある場合は、遺産分割の際、使い込みをした相続人の遺産の取り分を少なくしたり、返還を求めるといった対処方法を取るのが基本です。
ただ、使い込みをした相続人が親の介護を全面的に引き受けていたような場合は、使途不明金に相当する額はその謝礼のような意味合いになることもあります。
それにも関わらず、介護を全くやっていなかった相続人が、「使途不明金がある」と騒ぎ立ててしまうと、相続トラブルが却って大きくなる事態も考えられます。
もちろん、使い込みした金額が多額に上り、遺産がほとんど残っていない場合は、返還を求める必要がありますが、どのような対応が適切なのかは、ケースバイケースといえます。
使途不明金の用途と金額を確認する
看過できない使途不明金がある場合でも、すぐさま、預貯金を管理していた相続人を疑うのは避けたいところです。
「あなたが使ったんでしょ」といった決めつけをしてしまうと、遺産分割協議がこじれる原因になります。
まずは、預貯金の通帳や金融機関から取引履歴を取り寄せて、使途不明金の可能性のある金額を確認します。
介護費用や医療費等であれば、明細と照らし合わせることで使い道が判明しますし、大きな買い物をした場合も、買ったものや領収書が残っていれば、問題ないでしょう。
それ以外の使い道がはっきりしない金額を抜き出して、総額を出します。
また、被相続人が自分自身で預貯金の管理をすることが可能だったのは、どの時点までなのかという点もあわせて確認します。
被相続人が自分で管理していた時期の分は、被相続人が何かに使ったと考えられるため、使途不明金とは言えない可能性があります。
自分で管理できていなかった分は、使途不明金の可能性があるので、預貯金を管理していた相続人が使い込んだことを疑うことになります。
預貯金を管理していた相続人に使い道を確認する
使途不明金の額がはっきりしたら、預貯金を管理していた相続人に何に使ったのか確認します。
介護費用や医療費に充てたという主張なら、明細を求めたり、介護業者や病院に金額を確認するといった対応が必要です。
他の用途にしても、領収書を見せてもらったり、取引先にも金額を確かめるといった対応も必要です。
預貯金を管理していた相続人の主張に整合性がない場合は、相続人が使い込んだことによる使途不明金の疑いが強まります。
使途不明金相当額の返還を求める
使途不明金の疑いが強まった場合は、使い込みをした相続人にその金額の返還を求めるなどの対応を取ります。
その相続人が素直に認めた場合は、遺産分割協議で取り分を少なくしたり、任意に返還するよう求めるだけで解決できるかもしれません。
ところが、素直に認めない上に、遺産分割協議や返還にも応じない姿勢を示しているケースでは、相続人同士だけでの話し合いでは解決できないこともあります。
このような場合は、弁護士に相談したうえで、その後の対応策を検討する必要があります。
相続時の使途不明金の解決方法
相続の際の使途不明金の解決方法は、大きく分けると3つです。
- 交渉により解決する
- 遺産分割調停の中で解決する
- 不当利得返還請求などの訴訟を提起する
一つ一つ確認しましょう。
交渉により解決する
使途不明金に相当する金額は、不当利得返還請求などの訴訟を提起しなければ返還を求められないわけではありません。
使い込みをした相続人と交渉することで、任意の返還に応じてもらった場合は、返還された額次第で他の相続人も納得することもあるでしょう。
使い込みをした相続人の遺産の取り分を減らしたり、無くするという形で遺産分割協議がまとまることもあります。
相続人同士で話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼して交渉をまとめてもらうのも有効です。
遺産分割調停の中で解決する
使い込みをした相続人の遺産の取り分を減らす方向で話し合っているにも拘らず、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも検討します。
調停の場での直接の話し相手は調停委員で、相手の主張も調停委員を介して聞くことになります。
調停委員は解決策などを提案することもあります。その解決策に納得できる場合は調停が見込めます。
使い込みをした相続人の遺産の取り分を減らしてほしい場合は、その明確な証拠を示して、調停委員を納得させることが大切です。調停委員が納得すればその方向で話がまとまりやすくなります。
そのためには、弁護士に同席を求めたり、代理で出席してもらい、使途不明金が発生していることについて説明してもらうのが有効です。
不当利得返還請求などの訴訟を提起する
使い込みをした相続人から使途不明金を取り戻さないと遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停ではなく、簡易裁判所や地方裁判所に不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求の訴訟を提起します。
訴訟においては、使途不明金の額や使い込みについて、様々な証拠を示しながら主張、立証する必要があるので、弁護士に依頼しなければ、返還を求めることは難しいと言えます。
まとめ
相続では、被相続人の預貯金などを被相続人と同居していた相続人が管理していて、使い込みをしていることもあります。
これによって生じた使途不明金は、他の相続人が返還を求めることもできます。
でも、事情次第では、使途不明金であるとして争うのが適切ではないこともあります。
また、使途不明金の解決方法も、交渉、遺産分割調停、不当利得返還請求訴訟といくつかの手段があります。
どのような解決策が最善なのかは、ケースバイケースなので、判断が難しいことも多いものです。
相続に際して使途不明金が発生して困っている方は早めに弁護士にご相談ください。