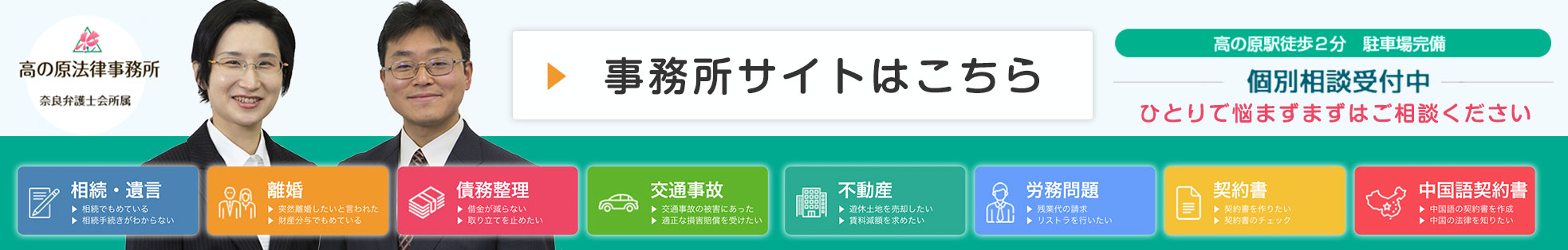コラム
遺留分は養子にも認められる?相続権の仕組みと対策をわかりやすく解説
養子にも遺留分は認められるか不安に思う方は多いです。普通養子と特別養子で異なる相続権の違いや、養子縁組を活用した遺留分対策、注意すべきポイントまで詳しく解説します。
相続について養子にも遺留分が認められるのか、不安を感じている方は少なくありません。
養子縁組をしても実子と同じ権利をもつのか、あるいは制限があるのか気になるところです。
相続の場面では、遺留分をめぐるトラブルが発生しやすく、正しい知識がないと不利益を被るかもしれません。
この記事では、遺留分の基本から養子縁組の種類や、養子縁組をした際の遺留分がどのように扱われるかを詳しく解説します。
また、養子縁組を利用した遺留分対策や、遺留分が認められないケースについても触れます。
相続の仕組みを理解し、事前の対策ができるようにしましょう。
そもそも遺留分とは
遺留分は、相続人が最低限の遺産の取り分を確保できる権利です。
相続人を保護することや、相続人同士の平等を実現することなどを目的とした制度です。
遺留分の権利をもつのは、配偶者・子・直系尊属のみであり、兄弟姉妹には認められません。
割合は、法定相続分の2分の1が基本です。
直系尊属(親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖)のみが相続人となる場合は3分の1です。
たとえば、相続人として子が2人いる場合、各自の法定相続分は2分の1となります。遺留分はさらにその2分の1となるため、4分の1です。
被相続人の意思(遺言書など)によっても奪えないため、遺留分を考慮した遺産分割の計画が重要といえるでしょう。
遺留分損害請求権とは
遺留分侵害額請求権は、相続人が遺留分を侵害された際に行使できる権利です(民法第1046条第1項)。
遺言や生前贈与によって遺留分が減らされた場合、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うように求めることが可能です。
この制度は、相続人の最低限の取り分を保障するために設けられており、一部の相続人に偏った遺産分配を防ぐ目的もあります。
遺留分を請求するには、相手方に対して請求の意思表示が必要です。
話し合いで解決しない場合、調停や訴訟によって請求額を確定させることになります。
請求できる期間には制限があり、相続開始および侵害を知った日から1年、または相続開始から10年以内に手続きを行わなければなりません。
養子縁組の定義と種類
養子縁組は、養親と養子の間に法律上の親子関係を成立させられる制度です。
養子縁組には下記の2種類があります。
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
それぞれについて解説します。
普通養子縁組
普通養子縁組は、法律上の親子関係を築く一般的な制度です。
実親との関係は継続したまま、新たに養親との親子関係となります。養子は養親の相続人となり、法定相続分や遺留分をもちます。
たとえば、夫婦が子どもを迎える場合や、孫を養子にして財産承継を円滑にするために利用されることが多いです
相続税対策の観点から、孫養子とするケースもあります。
実親との親子関係が維持されるため、養子は実親の相続にも関与できます。
特別養子
特別養子縁組は、子の福祉を最優先に考えた制度です。
実親との親子関係は完全に断たれ、養親のみが法律上の親となります。
普通養子縁組と異なり、成立には家庭裁判所の審判が必要です。
養親の年齢や養子の年齢に厳格な要件があり、主に実親が養育困難な子を対象とします。
相続に関しては、養親のみが法定相続関係に含まれます。
実親の相続権が消滅するため、養子は実親について遺留分を請求できません。
養子の遺留分
上述の通り養子は、普通養子か特別養子に関係なく実子と同じように遺留分が認められます。
養親の子として法定相続人となるため、遺言などによって財産を受け取れない場合でも一定の割合を請求できます。
遺留分割合は実子と同じく法定相続分の2分の1です。
養親に実子がいるケースでは、法定相続分は均等に分けられ、養子もその半分の遺留分を確保できます。
ただし、遺留分の請求については複雑な法的問題になるケースが多いため、専門家である弁護士に相談しながらすすめるのがよいでしょう。
養子の子の代襲相続はケースバイケース
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(被相続人の子など)が死亡している場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。
養子の子が養親の遺産を代襲相続できるかは、養子縁組された時期によって異なります。
養親(被相続人)と養子が養子縁組をする前に生まれた子(養子の子)は、養親の相続において代襲相続人とはなりません。一方で、養子縁組をした後に生まれた子(養子の子)は、代襲相続人となります。
養子縁組をして遺留分対策をするメリット
遺留分に関する対策として、養子縁組を検討するケースは少なくありません。
具体的には下記のようなメリットがあります。
- 相続をさせたくない子の遺留分を小さくできる
- 相続税の節税
それぞれについて解説いたします。
相続をさせたくない子の遺留分を小さくできる
養子縁組をすることで法定相続人の数が増え、相続させたくない子の遺留分を減らせます。
通常、法定相続人が少ない場合、その1人あたりの遺留分割合が大きくなるため、遺言などで「この人に多く渡したい」と考えても遺留分侵害額請求によって希望通りにいかないことがあります。
遺留分は法定相続分の2分の1で計算されるため、相続人の数が増えれば1人あたりの遺留分額が下がります(※)。
相続人が実子2人と配偶者の場合、子の遺留分は遺産全体の8分の1ですが、養子を迎えて相続人が3人になれば、それぞれの子の遺留分は12分の1です。
遺留分割合が下がれば、たとえば「介護をしてくれた子に多く渡したい」という希望を実現しやすくなるのです。
※法定相続分は配偶者2分の1、子は2分の1を子の人数分で割った数
相続税の節税
養子縁組を活用すれば、相続税の基礎控除額を増やせます。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人数×600万円」で計算されるため、養子が増えればその分控除額が大きくなります。
たとえば、法定相続人が実子1人のケースだと、基礎控除額は3,600万円ですが、養子を1人迎えると4,200万円です。
このように税負担を軽減する方法として、孫を養子にするケースも珍しくありません。
孫を養子にすれば相続税の計算上、1人分の基礎控除を増やせるだけでなく、相続税の2割加算の対象にもなりますが、世代をまたいで財産を承継できるメリットがあります。
ただし、昭和63年法律第109号による相続税法の改正以降、養子の数には相続税の課税に関して一定の制限が設けられています。
相続税法上、実子がいると養子1人まで、実子がいないケースでも養子2人までしか法定相続人として認められません。
養子縁組により相続人の数を増やし遺留分の割合を減らすことは法律上可能ですが、税務上の取扱いには別途で考える必要があります。
遺留分が認められない養子のケース
養子縁組をしていても遺留分が認められないケースも存在します。
主なケースは下記の4つです。
- 特別養子の実親からの相続の場合
- 偽造の養子縁組届が出されていた場合
- 養親に養子縁組できる能力がなかった場合
- 相続税対策の目的と判断された場合
養子縁組をすすめる際はこれらに該当しないように注意しなければなりません。
それぞれについて解説します。
特別養子の実親からの相続の場合
すでに解説したように特別養子は、実親と親子関係が法律上完全に消滅します。
特別養子となった時点で実親の戸籍から除籍され、養親のみが法的な親となります。
ただし、実親が遺言で特別養子に財産を遺すことは可能です。
しかし、遺留分侵害額請求の権利はなく、他の相続人がいる場合、遺産の取り分は制限されることがあります。
偽造の養子縁組届が出されていた場合
当然ですが、養子縁組届が偽造だった場合は法的に無効となります。
たとえば、養親の意思とは関係なく勝手に提出されたケースや、養親が知らぬ間に偽造された書類で養子縁組が成立していたケースでは、家庭裁判所で縁組無効の申し立てが認められます。
相続発生後に他の相続人が疑念を抱き、養子縁組の有効性を争うケースも少なくありません。
養親に養子縁組できる能力がなかった場合
養親に養子縁組をする能力がなかった場合、縁組自体が無効とされる可能性があります。
養親が認知症や精神疾患により判断能力を欠いていたと認められるなど、意思能力がない状態で縁組は成立しません。
養子縁組は契約行為の一種であり、当事者の合意が不可欠です。
養親が高度な認知症を発症していたり、日常生活の判断すら困難な状態で縁組が行われていたりした場合、後に親族が無効を主張できる可能性があります。
相続税対策の目的と判断された場合
相続税の節税のみを目的とした養子縁組も無効とされることがあります。
養子縁組により法定相続人が増えると、上述したように基礎控除額が拡大し相続税の負担が軽減されます。
しかし、税負担を減らす意図だけで養子縁組を行ったと判断されると、養子としての地位を否定される可能性があるのです。
養子としての実態があり、扶養関係や生活の実績が確認できる場合には問題となりません。
養子の遺留分について弁護士に依頼するメリット
養子の遺留分については、制度が複雑なため一般の人が対応していくには難しいケースも多いです。
養子のことや遺留分についてお悩みの際は専門家である弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談するメリットは下記のとおりです。
- 適切なサポートを受けられる
- 養子と他の相続人のトラブルを防ぎ早期解決できる
- 養子の立場に応じた遺留分請求の可否や戦略を示してもらえる
それぞれについて解説します。
適切なサポートを受けられる
養子が遺留分侵害額請求を検討する場合、法律上の正確な知識と手続きが不可欠です。
相続人である養子も遺留分が認められるケースは多くありますが、実際に請求をすすめるには相手方との交渉や必要書類の準備が重要です。
専門家に依頼すれば、相続関係の確認から証拠収集、請求書の作成まで一貫して任せられます。
相手側が話し合いに応じない場合や遺言内容が複雑なときも、法的な観点から具体的な行動を示してもらえるため、スムーズな請求が可能です。
請求後に相手方と交渉する際も、代理人として弁護士が対応することで、相手の態度が軟化するケースもあります。
書類不備で請求が無効になったり、交渉で不利になったりするリスクも回避できます。
養子と他の相続人のトラブルを防ぎ早期解決できる
養子が遺留分を主張すると、他の相続人と意見対立することが少なくありません。
実子や配偶者が遺産分割について不満をもつ場合、話し合いが難航しがちです。
弁護士に相談することで、第三者の立場から冷静に状況を整理し、適切な解決策を提示してもらえます。
調停や裁判など法的手続きも視野に入れたアドバイスを受けられるため、解決までの時間や負担も軽減されます。
養子の立場に応じた遺留分請求の可否や戦略を示してもらえる
養子であっても遺留分を請求できるかどうかは状況によって異なります。
被相続人が遺言で財産分配を指定している場合には、養子がどのように主張すべきかを慎重に判断する必要があります。
弁護士に相談すれば、養子としての法的地位を踏まえた具体的な方針や請求額の目安を示してもらえるため、無理のない現実的な対応が可能です。
【まとめ】養子の遺留分問題を解決するために
本記事では、養子の遺留分がどのように扱われるかや、養子縁組を利用した遺留分対策等について解説してきました。
本記事のポイントは下記の3つです。
- 養子も実子と同様に遺留分を請求できる
- 普通養子と特別養子で相続権の影響が異なる
- 遺留分対策として養子縁組は節税・権利調整に有効
養子の遺留分をめぐる問題は、相続で大きな影響を与えます。
養子も法定相続人として遺留分をもつため、他の相続人との関係を見据えた準備が欠かせません。
また、養子縁組の種類によって相続権が左右される点も見落とせません。
こうした状況を整理することで、トラブル防止や節税が実現できるのです。
とはいえ制度の理解や手続きは複雑なので、まずは弁護士への相談が確実な一歩になります。