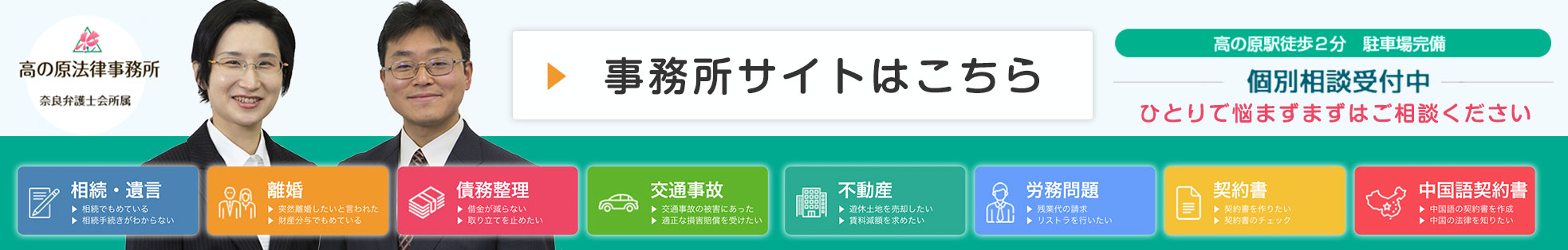コラム
相続時に銀行の預金口座を調べる方法は? 相続財産の調査方法について解説
相続が開始したら相続財産を調べる必要がありますが、銀行の預貯金の口座は最も大切な調査項目です。相続財産の調査を行わないと、相続人同士の遺産分割協議や相続放棄すべきかの判断、相続税の申告納税も行えなくなります。銀行の口座等、遺産を調査する方法について解説します。
相続開始後に銀行の預貯金の口座調査をするには? 相続財産の調査方法について解説
相続が開始した際は、遺産分割協議や相続税の納税申告の前提として、相続財産がどれだけあるのかの調査が必要です。
中でも、銀行の預貯金口座調査は確実に必要になりますが、被相続人が利用していた口座が分からない場合は、特定できないことがあります。
相続開始後に銀行の預貯金の口座調査をする方法と注意点について解説します。
相続時は遺産の調査が必要
被相続人が亡くなった際は、相続財産の確定のために遺産の調査が必要になります。
相続財産を確定しなければ、相続を承認すべきか、相続放棄すべきか、相続税がかかるのかどうか、遺産分割の対象となる財産は何なのかなどが分からないためです。
調査の対象となる財産は主に次のようなものです。
| プラスの相続財産 | 現金 銀行の預貯金 土地や建物の不動産 株式などの有価証券 高額な動産 貸付金などの債権 被相続人の生命保険金 |
|---|---|
| マイナスの相続財産 | 借入金 金融機関のローン 未払いの債務 保証債務 |
相続時の銀行の口座調査は困難なことが多い?
被相続人がエンディングノートなどで自分の遺産をまとめていない場合、遺産の調査は、困難を極めることが少なくありません。
意外に調査が難しいのが銀行口座です。
弁護士などの専門家に依頼すれば、どの銀行の口座にどれだけの預貯金があるのか、一括で調査できるとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には、すべての銀行の口座を一括で調査する方法はありません。
被相続人の行動範囲から口座を作りそうな銀行を特定して、銀行ごとに照会していくしかないのです。
相続時の銀行の口座調査方法は?
被相続人がお金を預けていた銀行口座は、地道に探していくしかありません。
誰でもできる具体的な調査方法を紹介します。
故人が銀行預金通帳やキャッシュカードを置いていた場所を調べる
今は、銀行預金をネットで管理する方も増えていますが、預金通帳を使っている方は依然として多いと思います。
まずは、故人が銀行の預金通帳やキャッシュカードを置いていた場所を調べましょう。
書斎の引き出しや金庫などが一般的ですが、へそくりなどの場合は、額の裏や神棚、食器棚などに入っていることもあります。
預金通帳やキャッシュカードを発見できれば、その銀行に口座があることが分かります。
故人宛の郵便物から使っている銀行を特定する
故人宛の郵便物もチェックしましょう。
銀行から直接来る郵便物はあまりないかもしれませんが、税金や公共料金のお知らせなどには、税金や料金の引き落としをしている銀行口座が書かれていることがあります。
また、年金を受け取っている場合は、年金関係のお知らせに年金が振り込まれている口座が書かれている事があります。
また、住宅ローンがある場合は、返済予定表や金銭消費貸借契約書、不動産登記簿の乙区の抵当権者からも取引銀行が判明することもあります。
故人のスマホやパソコンをチェックする
故人のスマホやパソコンも使っていた銀行の口座調査に役立ちます。
スマホならば、銀行のアプリを入れていることがありますし、パソコンでも使っている銀行をブックマークしていることがあります。
マイナンバー紐づけによる照会制度を利用する
現在では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」という法律により、銀行口座をマイナンバーと紐づけることができます(預貯金口座付番制度)。
そして、マイナンバーと紐づいている銀行口座については、相続時に、一ヵ所の銀行に問い合わせるだけで、他の銀行の口座の有無も一括で調べることが可能になっています。
ただ、銀行口座とマイナンバーの紐づけは、義務付けられているわけではないので、故人が利用していなかった場合は、この制度は活用できません。
故人の行動範囲内にある銀行に照会する
故人がどの銀行を使っていたのかはっきりしない場合の最終手段が、故人の行動範囲内にある銀行をリストアップして、しらみつぶしに銀行口座の有無を問い合わせることです。
また、ネットだけで開設できる銀行口座も利用している可能性があるため、ネット銀行も確認が必要です。
被相続人の銀行口座を特定した後で調査すべきこと
被相続人の銀行口座を特定した後は、次の2点について調査を行います。
- 現在の預貯金の残高照会
- 現在までの取引履歴の照会
一つ一つ確認しましょう。
現在の預貯金の残高照会
被相続人の死亡時の預貯金の残高を確認することで、相続の対象となる財産の価額を確定します。残高を示す証明である残高証明書を発行してもらいましょう。
なお、被相続人の銀行口座であることが確認できた時は、他の相続人が勝手に引き出ししないように口座の凍結を行ってもらいます。
現在までの取引履歴の照会
被相続人の死亡時の預貯金の残高だけでなく、過去の取引履歴の調査も重要です。
被相続人が入院していた場合などは、その間、身近にいた人が銀行口座を管理していた可能性があります。
相続人の一人が管理していた場合は使い込みをしている可能性もあります。
また、何に使ったのかよく分からない使途不明金が発覚することもあります。
さらに、特定の相続人に多額の預金を贈与している場合は、特別受益に当たるものとして相続の対象となる財産の価額を確定する際に持ち戻しを行うこともあります。
取引履歴は通帳やネットの取引一覧でも把握できますが、正式に証明する書類として、取引履歴明細証明書等を発行してもらいましょう。
被相続人の銀行口座が解約されていた場合は?
被相続人の銀行口座を調査していると、過去に預貯金を預けていたけど、死亡時には既に解約済みの口座が判明することもあります。
この場合、被相続人の死亡時点では、預貯金がないことになるため、相続の対象となる財産の価額には影響しません。
ただ、過去の取引履歴の調査は必要です。
被相続人が亡くなる直前の時期に解約されていた場合は、被相続人の財産を管理していた人が使い込みしていた可能性が否定できませんし、過去に特別受益に当たる贈与などを行っていた可能性もあるためです。
特別受益に当たる贈与が判明した時は、相続の対象となる財産の価額も影響を受けます。
被相続人の銀行口座調査に必要なもの
被相続人の銀行口座調査は、各金融機関の窓口で口頭で問い合わせただけでは教えてもらえません。
必要な書類をそろえるように求められるのが一般的です。そのため、調査に先立って必要な書類はあらかじめそろえておくとスムーズに手続きを進められます。
主に必要になるのは次のような書類です。
- 被相続人の死亡を証する戸籍謄本
- 依頼者が相続人であることを証する戸籍謄本
- 依頼者する相続人の印鑑証明書
一つ一つ確認しましょう。
被相続人の死亡を証する戸籍謄本
被相続人が亡くなったことは、死亡届を提出することで市区町村役場で戸籍に情報を反映させます。
死亡届を提出してすぐに反映されるわけではないため、1週間程度経ってから、戸籍謄本等を取得しましょう。
依頼者が相続人であることを証する戸籍謄本
銀行口座調査を依頼する人と被相続人のつながりが分かる戸籍謄本が必要になります。
一般的には、ご自身の現在の戸籍謄本と被相続人の死亡を証する戸籍謄本を突き合わせれば、被相続人とのつながりが分かります。
依頼者する相続人の印鑑証明書
依頼者の身元を確認するために必要になります。免許証やマイナンバーカードなどの提示を求められることもあります。
被相続人の銀行口座調査を依頼する際の注意点
金融機関に被相続人の銀行口座調査を依頼する際に注意するべきことは、被相続人の死亡を知ると金融機関は直ちに口座を凍結してしまうことです。
その金融機関の口座で公共料金を引き落としている場合や何らかの振り込みがなされている場合は、先に引き落し口座や振込口座の変更等の手続きを行っておく必要があります。
また、葬儀費用、入院費用、介護費用の支払いや清算などでまとまった金額の支払いのために、被相続人の名義の銀行口座から引き出さなければならないこともあります。
こうした理由で、引き出しを行う場合は、使い込みを疑われないように他の相続人の了解も得た上で、必要な金額を先に引き出しておきましょう。
被相続人の銀行口座調査を行わなかった場合
被相続人の銀行口座を特定するのが面倒だからと、調査を行わなかった場合は様々な相続トラブルに発展する可能性があります。
被相続人の預貯金に関する遺産分割ができない
被相続人の預貯金について遺産分割協議を行うことができません。
この場合、被相続人の預貯金はないものとして遺産分割協議を行うことになりますが、後で、銀行口座が判明した場合、見つけた人がこっそりと自分のものにしてしまう可能性もあります。
特別受益の主張や使途不明金の追及ができなくなる
特定の相続人が被相続人の銀行口座から多額の預金の贈与を受けていた場合は、その取引履歴を基に、特別受益に当たるといった主張を行います。
また、特定の相続人が使い込みしていることによる使途不明金を追及する際も、銀行預金等の取引履歴が必要です。
ところが、贈与や使い込みに使われた銀行口座を特定できなければ、そうした主張を行うことさえできなくなります。
遺産分割協議をやり直さなければならないこともある
遺産分割協議が終わった後で被相続人の銀行口座が判明した場合は、銀行口座に預けられている金額について、改めて遺産分割協議を行う必要があります。
預貯金を法定相続分で分割するだけで話がまとまるとは限りません。
特に、過去の取引履歴から特別受益が発覚した場合は、持ち戻したうえで、遺産分割を行わなければなりません。
先に行った遺産分割の内容が不公平だといった話が噴出してしまい、改めて、すべての遺産について遺産分割をやり直さなければならないこともあります。
相続税の申告漏れや追徴課税になる可能性がある
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。一般的には、被相続人が亡くなった日から10カ月以内です。
被相続人の銀行口座調査を行わず、10カ月経過した後で、銀行口座が判明した上、相続税の申告と納税が必要になるほどの大金が残されていた場合は、相続税の申告漏れに該当してしまいます。
この場合、追徴課税を受けてしまうため、本来支払えばよい相続税の税額よりも多額の税金を支払わなければならないことになります。
相続時の銀行の口座調査はいつまでに行えばよいのか?
相続時の銀行の口座調査をいつまでやるべきかという法律上の決まりはありません。
ただ、様々な相続手続きの期限があるため、その期限を意識して銀行の口座調査を行う必要があります。
相続開始から3ヶ月
相続人になった場合、相続開始から3ヶ月経過するまでの間に、相続について、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの選択をしなければなりません。
特に、被相続人に借金などの負債がある場合は、相続放棄すべきかどうか検討することになりますが、その判断に当たっては、プラスの相続財産がどれだけあるのか確定する必要があります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、速やかに被相続人の銀行口座調査を行わなければなりません。
相続開始から10ヶ月
相続開始から10ヶ月経過するまでの間に、相続税の申告と納税を済ませなければなりません。
相続税の申告と納税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に必要になります。
具体的には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額を超えている場合です。
遺産の総額がこの金額を超える可能性がある場合は、被相続人の銀行口座調査をしっかりと行って、相続税の申告漏れにならないように注意する必要があります。
相続時に銀行口座調査で困らないように生前にできる事とは?
相続人が相続の際、銀行口座調査で困ってしまうのは、被相続人がどの銀行口座を使っていたのか分からない場合です。
特に、被相続人しか知らないへそくりについては、本人が誰かに教えない限り、発見されないままになってしまうこともあります。
こうした事態を避けるためには、被相続人の方が生前に、エンディングノート等を活用しながら、自分が使っている銀行口座のリストを作成しておくことが大切です。
また、銀行口座がたくさんある場合は解約を進めて、少数の口座にまとめておくことも検討しましょう。
まとめ
現在、相続が開始しており銀行口座の調査で困っている場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
相続財産のほとんどは、銀行の預貯金、株式、投資信託、不動産の4つで占めていますが、この中でも銀行の預貯金は、ほとんどの被相続人が確実に有しています。
ただ、どの銀行口座を利用していたのかが全く分からない場合は、調べようがないこともあるのではないでしょうか。
そんな時でも、相続問題に詳しい弁護士なら、調査方法のノウハウを有しているため、銀行口座の特定が可能です。
相続において、銀行の口座調査でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。