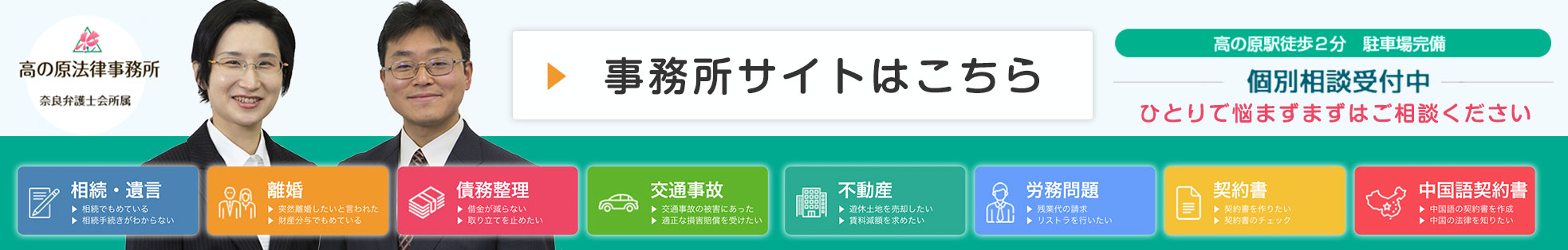コラム
遺留分侵害額請求がなされた場合はどう対処すべき? 相続トラブルの対処法を解説
遺言により相続の割合が決められた場合や生前贈与がある場合は、不満のある相続人から遺留分侵害額請求がなされてしまうことがあります。遺留分を請求された場合は相続トラブルに発展するリスクが高いので早めに弁護士に相談すべきです。遺留分を請求された際の対応について解説します。
遺留分を請求された際の対処方法や流れを解説
遺言により相続の割合が決められた場合や多額の生前贈与がある場合は、不満を持つ相続人が現れることもあります。このような場合、遺産を相続できなかったり、取り分が少ない相続人が遺留分侵害額の請求を行うこともあります。
遺留分を請求されたケースでは、相続トラブルに発展するリスクが高いため、早めに弁護士に相談すべきです。
この記事では、遺留分の請求を受けた方が慌てず対応するためのポイントについて解説します。
遺留分とは何か?
民法では、法定相続分と言い、相続人の立場に応じて相続できる割合が決められています。
ただ、法定相続分は絶対的なルールではなく、被相続人が遺言により相続させたい人を自由に決めても構いませんし、遺産分割協議でも、相続人の取り分を自由に決めてよいことになっています。
しかし、相続人によっては、被相続人の財産を頼りに生活している人もいますし、全く取り分がないと不公平になってしまうこともあります。
そこで、一定の法定相続人には最低限の取り分として、遺留分が認められています。
遺留分が認められる相続人とは?
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には次の人たちです。
- 配偶者
- 子、孫などの直系卑属
- 両親、祖父母などの直系尊属
遺留分として認められるのは、原則として、それぞれの法定相続分の2分の1です。
両親、祖父母などの直系尊属のみが法定相続人として残っている場合は3分の1になります。
例えば、法定相続人が次の方たちだとしたら、それぞれの法定相続分と遺留分の割合は次のようになります。
| 法定相続分 | 遺留分 | |
| 配偶者 | 2分の1 | 2分の1×2分の1=4分の1 |
| 長男 | 6分の1 | 6分の1×2分の1=12分の1 |
| 長女 | 6分の1 | 6分の1×2分の1=12分の1 |
| 次男 | 6分の1 | 6分の1×2分の1=12分の1 |
遺留分を請求される人とは?
遺留分を請求される人は、受遺者または受贈者です。
受遺者とは、遺言によって遺贈を受けた人。
受贈者とは、生前贈与を受けている人を意味します。
受遺者または受贈者には、相続人となった人も含みます。
代表的なケースとしては、相続人の一人が遺言によりすべての遺産を相続している場合です。他の相続人から遺留分について請求される可能性があります。
特別受益を受けた人は、他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。
なお、生前贈与の分については、過去の生前贈与すべてが対象となるわけではありません。
相続人以外の方への生前贈与については、相続開始前の1年間になされた分だけが対象になります。
相続人に対する生前贈与については、相続開始前の10年間になされた分が対象になります。また、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限定されます。
遺留分侵害額請求とは?
遺言や生前贈与が法定相続人の遺留分を侵害していても、無効になるわけではありません。
遺留分相当額の遺産を相続できなかった人が、受遺者または受贈者を相手に、遺留分侵害額請求権という権利を行使する形になります。
具体的には、自分の遺留分の侵害を受けている相続人が、受遺者または受贈者を相手に、侵害された遺留分の割合に相当する金銭の支払いを求めます。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いは?
少し前までは、遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求と呼ばれていました。
どちらも遺留分の侵害を受けている相続人が行使できる権利であることに変わりはありません。
大きな違いは、遺留分減殺請求では、相続した財産をそのまま返す必要があったということです。
例えば、不動産を相続したことで遺留分を侵害した場合ですと、その不動産を遺留分減殺請求権を行使した相続人に返還しなければなりません。
不動産全部が対象ではなく、持分が対象の場合は、遺留分減殺請求の結果、相続人による不動産の共有という好ましくない状況になることもありました。
現在の遺留分侵害額請求では、相続した財産をそのまま返す必要はなく、金銭的な返還だけでよいことになっています。
不動産を相続したことで遺留分を侵害した場合でも、遺留分の割合に相当する金銭を支払えばよく、不動産を引き渡したり、不動産の持分を譲渡して共有状態にする必要はなくなりました。
遺留分侵害額を請求する際の流れ
遺留分侵害を主張したい相続人が、遺留分侵害額請求を行う場合の流れを確認しましょう。
遺留分侵害額の計算
遺留分侵害を主張するにあたっては、遺留分侵害額を計算することが必要です。
そのためには、次の3つを確定する必要があります。
- 今回の相続の法定相続人
- 相続開始時の相続財産の額の確認
- 持ち戻しの対象となる生前贈与の額の計算
これらの人物や数字を確定したうえで、自分の遺留分の侵害を受けている相続人が、遺留分侵害額の具体的な金額を計算します。
遺留分を侵害している人の特定
具体的に誰が遺留分を侵害するほどの遺贈や生前贈与を受けているのかを特定します。
法定相続人の一人が全財産を遺贈されているといった事例では、考えるまでもありません。
しかし、それぞれの法定相続人の遺産の取り分があるものの、その取り分に差があるために、自分の遺留分の侵害を受けているケースでは、遺留分侵害の請求を行うべき相手は誰なのかよく検討する必要があります。
遺留分侵害額の請求
遺留分侵害額、さらに、遺留分の侵害をしている人を特定した後で、遺留分侵害額請求権を行使します。
遺留分侵害額請求権を行使した日付が明らかになるように内容証明郵便を用いるのが一般的です。
当事者間の交渉
遺留分の侵害を受けている人と遺留分を侵害している人との間で、交渉が行われます。
交渉は裁判で行わなければならないというルールはなく、双方が話し合いにより解決することも可能です。
遺留分侵害額の請求調停
当事者間の交渉で話し合いがまとまらないケースでは、自分の遺留分の侵害を受けている人が、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てることが多いです。
調停では、調停委員を介して、当事者双方が話し合いを行っていきます。
遺留分の侵害が明確であれば、多くの場合、この調停手続によって解決します。
調停が成立すれば、調停調書が作成されるので、この調停調書に基づいて、具体的な清算が行われます。
なお、調停は、当事者が話し合って解決するのを家庭裁判所が手助けする制度でしかありません。
当事者双方が納得できない場合は、調整不成立になり、解決できないままになります。
また、遺留分侵害額の請求を行うことの他、遺産分割をめぐる争いが生じている場合は、遺産分割調停を申し立てることもできます。
遺産分割調停の中で、遺留分侵害額の問題が持ち上がれば、まとめて話し合いが行われます。
遺産分割調停も、相続人同士が話し合って納得した場合のみ調停が成立します。
当事者双方が納得できない場合は、調停不成立になります。
ただ、遺留分侵害額の請求調停と異なり、遺産分割調停では調停不成立の場合、自動的に審判手続が開始されます。
審判とは、家庭裁判所の裁判官が話し合いの経緯を踏まえた上で、様々な事情を考慮して、審判という形で結論を出すものです。
判決に似た効力がありますが、もし、審判の内容に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告を行うことができます。
遺留分侵害額請求訴訟の提起
遺留分侵害額の請求調停が不成立となった場合は、地方裁判所又は簡易裁判所に対して民事訴訟を提起することもあります。
遺留分侵害額請求訴訟と呼ばれる訴訟です。
訴訟が提起されると、自分の遺留分の侵害を受けているのか、具体的な金額を示しての審理になります。
遺留分侵害額を請求したい側(原告)が遺留分侵害額について、主張し、立証するので、請求された側(被告)は、遺留分侵害はないとか、金額がおかしいといった主張を行います。
裁判官は双方の主張を基に訴訟上の和解を提案したり、判決を下します。
訴訟上の和解に対して、双方が受け入れた場合は、和解調書が作成されて、訴訟が終了します。
判決が出された場合は、判決書の送達から2週間経過することで判決が確定します。
判決に不服がある場合は、2週間以内に控訴を行い、控訴審での裁判が続けられます。
遺留分侵害額請求を受けた場合のチェックポイント
あなたが遺留分侵害額の請求を受ける立場の場合は、慌てずに、相手の主張に理があるのかどうかよく検討しましょう。
その際にチェックすべきポイントを解説します。
遺留分侵害額請求権を行使している人に権利があるのかどうか?
遺留分侵害額請求権を行使している人にその権利があるのかよく確認しましょう。
遺留分侵害額請求権は法定相続人全員に認められている権利ではありません。
特に、被相続人の兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権は認められていません。
代表的なケースは子のいない夫婦の一方が亡くなり、配偶者と兄弟姉妹が相続人になった場合です。
子のいない夫婦で被相続人の両親も既に他界している場合は、原則として配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹の法定相続分は、4分の1なので、遺産分割協議によって遺産を分け合わなければなりません。
ただ、被相続人が生前に、配偶者に対して全遺産を相続させる旨の遺言を残していた場合は、配偶者は全遺産を相続することができます。そして、兄弟姉妹には、遺留分がないため、兄弟姉妹より遺留分侵害額の請求がなされても無視することができます。
あなたが遺留分を支払わなければならないのか?
あなたが遺留分を支払わなければならない立場なのか、よく検討する必要があります。
遺留分侵害額請求の順番については、民法1047条にルールが定められています。
具体的には次のとおりです。
- 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
- 受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
- 受遺者又は受贈者が複数で、贈与が同時になされている場合は、贈与の価額の割合に応じて負担する。
例えば、あなたの生前贈与分に関して、遺留分侵害額の請求を受けているケースでは、あなたよりも先に遺留分侵害額を負担すべき人がいる可能性があります。
このような場合は、安易に応じるのではなく、弁護士に相談するなどして、よく検討することが大切です。
遺留分侵害額請求権の消滅時効期間や除斥期間を経過していないかどうか?
遺留分侵害額請求権は、遺言書などにより、いったん確定したはずの相続関係に大きな影響を及ぼす制度であるため、権利行使できる期間が限定されています。
民法1048条に次のように消滅時効期間や除斥期間が定められています。
- 消滅時効期間:相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを遺留分権利者が知った時から1年が経過した時。
- 除斥期間:相続開始の時から10年を経過した時。
一般的には、被相続人が亡くなってから、1年が経過した時は、遺留分侵害額請求権は時効により消滅している可能性があります。
そのため、その日以降に遺留分侵害額請求を受けたケースでは、そもそも応じなくてよい可能性があります。
なお、遺留分権利者が1年以内に権利行使したかどうかは、内容証明郵便の日付により、判断するのが一般的です。
内容証明郵便を受け取っておらず、口頭で請求を受けているだけであれば、1年経過してしまえば、対応する必要はなくなります。
遺留分侵害額の請求金額が適正なのかどうか?
遺留分侵害額の計算方法は、複雑なので、慣れていない方が計算しても、その計算方法が間違っていることもあります。
遺留分侵害額の具体的な金額は、「遺留分を算定するための財産の価額×遺留分を侵害された人の遺留分の割合」によって計算することができます。
これによって計算した金額すべてを請求できるわけではなくて、「遺留分の侵害を受けている人が相続したり、遺贈や生前贈与を受けた金額」を差し引きます。
つまり、自分の遺留分の侵害を受けていると主張している人が、今回の相続では遺産相続できなくても、生前贈与を受けていれば、遺留分相当額を既に受け取っている可能性があります。
また、遺留分を算定するための財産の価額についても、過大に計算している可能性があるため、この計算が正しいのかどうかよく検討する必要があります。
遺留分侵害額請求を受けた場合の対処方法
遺留分侵害額請求権の行使が適正なものであるケースでは、無視することはできません。
遺留分侵害額請求権者との交渉や調停を行う必要があります。
そして、遺留分侵害額として請求を受けた金額が適正である場合は、その金額については支払いに応じるしかありません。
ただ、支払いが難しい場合は、次のような対処方法を検討しましょう。
遺留分侵害額請求権者が相続した債務の免責的債務引受けを行う
遺留分侵害額請求権者が被相続人の負債を相続しているケースでは、その負債の分、請求額が増額されている可能性があります。
このようなケースでは、遺留分侵害額請求権者が相続した負債について、あなたが引き受けることで、請求額を減らせる可能性があります。
裁判所に期限の許与を請求する
直ちに請求された額を支払うことが難しい場合は、裁判所に、全部又は一部の支払について、相当の期限を許与するように求めることができます(民法1047条5項)。
まとめ
遺留分侵害額請求を受けた際は、どのように対処してよいのか分からないことも多いと思います。
遺留分侵害額請求権の権利行使の方法は複雑なので、請求権者の主張が正しいとは限りません。
また、遺留分侵害額の具体的な計算も正しいとは限りません。
遺留分侵害額請求を受けた場合でも安易に応じるのではなく、請求内容が正しいのかよく検討することが大切です。
しかし、判断が難しい場合が多いと思いますので、遺留分侵害額請求に関するトラブルに発展している場合は、早めに相続トラブルに詳しい弁護士にご相談ください。