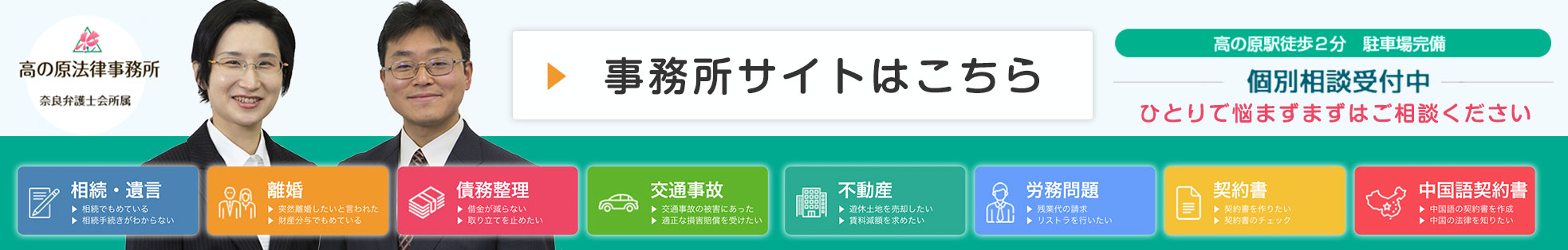コラム
被相続人の銀行口座、貯金から葬儀費用の引き出しをする方法と注意点について解説
相続手続きの開始前に葬儀費用を支払う必要がある場合は、被相続人の銀行口座、預金から引き出すこともあります。この場合、法定相続分の3分の1、150万円までが限度です。葬儀費用を被相続人の預貯金から出すことの法的な問題点や注意点、凍結された場合の引き出し方法についても解説します。
相続手続きの前に葬儀費用分について引き出しを行う方法と法的リスクについて解説
被相続人が亡くなった時は、相続手続きの前に、葬儀費用をどのように工面するかという問題が生じます。
多額の葬儀費用がかかる時は、被相続人の銀行預貯金口座などから引き出しをしなければならないこともあります。
そもそも、相続手続きをする前に被相続人の銀行預貯金口座から葬儀費用相当額の引き出しを行うことができるのでしょうか?
この記事では、相続における葬儀費用の引き出しの問題について解説します。
葬儀費用の相場とは?
葬儀費用の相場は、約100万円〜200万円とされています。
これだけの費用がかかるため、喪主自身が負担することは難しく、被相続人の預貯金から葬儀費用の相当額を引き出したいというケースも少なくありません。
葬儀費用を調達する方法は?
葬儀費用を調達する方法は様々ですが故人が生前に準備していたかどうかにより、大きく異なります。
具体的な方法を見ていきましょう。
香典を葬儀費用の支払いに充てる
お通夜や葬儀の当日に、会葬者から喪主に香典が渡されることがあります。
この香典は、喪主への贈与にあたりますが、葬儀の負担を軽減する意味合いもあります。そのため、香典を葬儀費用の支払いに充てることはよくあることです。
香典だけで葬儀費用をすべて賄えるわけではありませんが、かなりの負担軽減になります。
健康保険の葬祭費・埋葬料を受け取る
故人が健康保険の被保険者であれば、遺族の方が葬祭費や埋葬料を受け取ることができます。
国民健康保険の加入者であれば葬祭費、協会けんぽなどの社会保険の加入者であれば埋葬料が支給されます。
一般的には葬祭費・埋葬料は5万円程度ですし、受取りのためには、市区町村役場や社会保険事務所などで申請を行わなければなりません。
また、実際に受け取れるのは、葬儀後、申請を終えてから1〜2ヶ月程度経った後なので、葬儀費用そのものに当てることは難しいのが一般的です。
喪主が負担する
故人が葬儀のための資金を生前に用意していなかった時は、喪主が負担するしかありません。
なお、葬儀費用は喪主と葬儀会社の間で、葬儀の契約を行うことにより生じるもので、基本的に相続とは関係ありません。
そのため、葬儀費用を喪主が負担しても、喪主は、故人の相続財産の中から、葬儀費用相当額を先取りできるわけではありません。
葬祭ローンを利用する
喪主が、葬儀費用を一括して支払うことが難しい場合は、金融機関などから葬儀費用を借りて葬祭ローンを組むことも可能です。
葬祭ローンは、葬儀会社と金融機関などが提携して実施していることがあります。
分割払いが可能になるので、一括払いが難しいケースでは有効な選択肢です。
ただし、分割払いで最終的に支払う金額は一括払いより多額になることに留意しましょう。
金融機関等からお金を借りる
消費者金融やクレジットカード会社などのカードローンを利用したり、キャッシング枠を利用するなどしてお金を借りる方法です。
借りたお金の使い道は、特に決まりはないため、葬儀費用に当てることも可能です。
ただ、返済時は利息を上乗せして返さなければならないため、トータルの出費が増えてしまいます。
葬儀費用を被相続人の銀行口座から引き出しする時の注意点
葬儀費用は、葬儀が終わった後、1週間前後で支払わなければならないのが一般的です。喪主が自分の預金口座などから支払えない場合は、被相続人の銀行預金口座から引き出しを行うこともあります。
この場合に注意すべきことをまとめます。
被相続人の預金口座は凍結される
被相続人の預金口座は、被相続人が死亡した後で凍結されるのが一般的です。
具体的な時期は、相続人等が被相続人が死亡した旨を金融機関に知らせた時です。
例えば、
- 相続人等が銀行の窓口に赴いて被相続人が死亡した旨を知らせた時。
- 相続人等が銀行に相続手続きの問い合わせをした時。
- 相続人等が残高証明書の取得申請をした時。
- 相続人等が被相続人名義の口座の有無を問い合わせた時。
などに金融機関の方で口座を凍結します。
葬儀費用を引き出す前に、被相続人の死亡を知らせてしまうと、預金口座が凍結されてしまうため、引き出しができなくなるので注意してください。
なお、一つの金融機関に被相続人の死亡を伝えると他の金融機関の口座も凍結されるという扱いにはなっていません。
口座の凍結の手続きは金融機関ごとに個別に行います。
また、金融機関の口座と紐づいている社会保険や年金関係の手続きを行っても、それだけで銀行口座が凍結されるわけではありません。
例えば、被相続人が金融機関の口座で年金を受け取っていた場合であれば、死亡後は、その口座に年金が振り込まれなくなりますが、その動きから、金融機関が死亡を察して口座を凍結するといった事例は基本的にありません。
遺産の使い込みや横領を疑われる
相続人の一人が、葬儀費用を支払うために無断で被相続人の銀行預金口座から引き出しを行うと、他の相続人から遺産の使い込みや横領を疑われるリスクがあります。
この場合、遺産分割協議で被相続人の口座から勝手に引き出したと追及されてしまい、話し合いがまとまらなくなることもあります。
特に、その相続人が生前から被相続人の口座を管理していた場合は、生前の引き出しについても疑われてしまうこともあります。
相続放棄ができなくなることもある
被相続人が莫大な借金を抱えていた場合は、相続人が単純承認すると負債を相続してしまうおそれがあります。
銀行口座に預金が残っているケースでも思わぬ借金を抱えていることは少なくありません。
このような場合は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことで、負債を相続することを防ぐことができます。
ところが、被相続人の死亡後に銀行口座から葬儀費用を引き出すと、単純承認したものと判断されてしまい、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。
被相続人の銀行口座から預金を引き出した場合は、民法921条の法定単純承認に該当する可能性があるためです。
銀行口座の凍結後に葬儀費用を引き出すには?
被相続人の銀行口座が凍結された後になって葬儀費用を引き出すには2つの方法があります。
預金の仮払い制度と家庭裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分の申立を行う方法です。それぞれ確認しましょう。
預金の仮払い制度を利用する
被相続人が亡くなった後は、被相続人の預貯金は遺産分割協議を終えて、各相続人の取り分が決まるまでは、勝手に引き出すことができないのが原則です。
ただ、当面の生計費、平均的な葬式費用などのためであれば、各相続人が被相続人の預貯金口座から一定の金銭を引き出すことができます。
これを遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)といい、民法909条の2に基づく権利です。
具体的な金額は次のいずれか少ない額です。
- 被相続人の死亡時の預金残高✕1/3✕預金を引き出す相続人の法定相続分の割合
- 150万円(民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)
具体例で確認しましょう。
Aさんが亡くなり、銀行に1500万円の預金が残されていたとします。
Aさんの法定相続人が、妻Bさん、子のCさん、Dさんの3人だったとします。
この場合それぞれの法定相続分の割合は次のようになります。
| 妻Bさん | 2/4 |
|---|---|
| 子のCさん、Dさん | 1/4 |
そして、上記の計算式に当てはめると次のようになります。
| 妻Bさん | 1500万円 ✕ 1/3 ✕ 2/4 = 250万円 |
|---|---|
| 子のCさん、Dさん | 1500万円 ✕ 1/3 ✕ 1/4 = 125万円 |
なお、省令により150万円が限度とされているため、妻Bさんが引き出せる額は150万円に限られます。
つまり、この事例では、妻Bさんは150万円、子のCさん、Dさんは125万円まで引き出しできるということです。
預金の仮払い制度を利用した場合の注意点
民法909条の2に基づく預金の仮払い制度を利用した場合は、相続人がこれによって得た金銭については、遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなされることに注意しましょう。
つまり、遺産分割協議では、原則として、引き出した金額分だけ取り分が少なくなるということです。
例えば、上記の事例で、妻Bさんが150万円を引き出したケースでは、その後の遺産分割では原則として、次のように分けることになります。
| 妻Bさん | 750万円 − 150万円 = 600万円 |
|---|---|
| 子のCさん、Dさん | 375万円 |
家庭裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分の申立を行う
預金の仮払い制度では、150万円が限度になります。
そのため、葬儀費用として150万円以上かかった場合は、これだけでは足りないこともあります。
このような場合は、家庭裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分の申立を行う方法もあります。
具体的には、
- 家庭裁判所に遺産分割の調停の申立を行う。
- 葬儀費用を支払うために遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるとして預貯金債権の仮分割の仮処分の申立を行う。
という流れになります。
こちらの制度は、遺産分割調停の申立を行っていることが前提となるため、やや使いづらい制度です。
生前に葬儀費用のためにできることは
葬儀費用を巡って相続トラブルが発生することを防ぐためには、被相続人が葬儀費用について生前に準備しておくことが大切です。
具体的には次の2つの方法が検討されます。
- 被相続人が葬儀費用を用意しておく
- 葬儀保険に加入しておく
一つずつ確認しましょう。
被相続人が葬儀費用を用意しておく
葬儀費用に関して、相続人や遺族が困らないようにするためには、被相続人や故人が葬儀費用を生前に用意しておくのが最善です。
もっとも、亡くなる直前に自分で銀行に赴いて預貯金を引き出すことは現実的ではありませんので、あらかじめ遺言書を用意し、「私の葬儀費用は私の銀行口座から支出してほしい」といった付言事項を記載しておくとよいでしょう。
そうすれば、相続人がためらうことなく相続財産の中から葬儀費用を出すことができます。
相続人が立て替え払いした場合でも、遺産分割に先立って、立て替え払いした分をその相続人が受け取ることができます。
葬儀保険に加入しておく
葬儀費用を出すための葬儀保険というものもあります。
保険金の額は葬儀に必要な100万円程度と少なめですが、その分、月々の掛け金も少ないですし、高齢者でも加入しやすく、医師の診断も必要ないこともあります。
ただ、月々支払う掛け金は、掛け捨てになり、貯蓄性はありません。
長く加入している場合は、払い込んだ掛け金の総額が保険金の額を上回ってしまうこともあります。
また、更新できる年齢の上限が設けられていたり、更新の度に掛け金が値上がりすることもあります。
そうした点を考慮したうえで、自分に合う葬儀保険がある場合は加入を検討するとよいでしょう。
被相続人の銀行預金口座から葬儀費用を引き出す時にやるべきことは?
相続人である喪主が被相続人の銀行預金口座から葬儀費用を引き出す時にやるべきことは次の3つです。
- 他の相続人の承諾を得る
- 葬儀費用の領収書をもらう
- 余った金銭は保管する
一つ一つ確認しましょう。
他の相続人の承諾を得る
相続人である喪主が被相続人の銀行預金口座から葬儀費用を引き出す時は、無断で引き出すのではなく、他の相続人にもその旨を伝えて、承諾を得ておきましょう。
葬儀費用の見積書と領収書を保管する
葬儀費用については、葬儀会社が見積書や請求書を用意してくれるので、その金額を元に引き出す金額を決めましょう。
また、葬儀費用を支払ったら、領収書をもらえるので、その領収書を保管しておきましょう。
余った金銭は保管する
葬儀会社に見積書を用意してもらっても、葬儀の前後では予想外の出費がある事も考えられるため、多めに引き出すこともあるでしょう。
その場合でも、余ったお金を引き出した相続人のものとするのではなく、保管しておきましょう。
このようにして、葬儀費用の引き出しについて使い込みや横領を疑われる事態を防ぐことが大切です。
まとめ
被相続人が亡くなった際は、葬儀費用として数百万円といった金額がかかるため、被相続人の銀行等の預貯金口座から引き出しを行う必要があることもあります。
ただ、被相続人の口座から勝手に引き出すことは、相続トラブルの原因となりやすいので注意しましょう。
葬儀費用の引き出しを巡って相続トラブルが生じている時は弁護士にご相談ください。