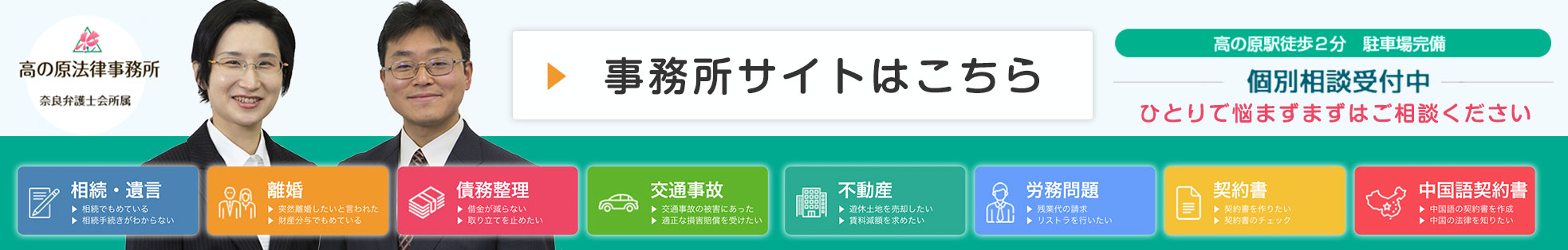コラム
家族信託の相続における活用方法とは? 手続きやメリット・デメリットも解説
家族信託は、財産を持つ委託者が受託者に財産管理を委託し、受益者が管理運用による利益を受ける仕組みの事です。認知症で判断能力が衰えた人のための成年後見制度に代わる制度ですが、二次相続対策、生前贈与の仕組みとしても利用されています。相続対策としての家族信託の有効な活用方法とは? について解説します。
【家族信託と相続】家族信託の有効な活用方法やメリットとデメリットを解説
家族信託は、財産管理制度の一つで、成年後見制度、任意後見制度に代わる制度として活用されていますが、相続対策としても使えます。
特に二次相続対策や生前に財産を相続人である受託者に移転してしまうことにより、相続発生時の手続きの手間を省くことも可能です。
家族信託の相続における有効な活用方法やメリットとデメリットについて解説します。
家族信託とは
家族信託とは、多額の財産を持っている方が、財産の管理や処分を信頼できる家族などに任せる制度です。
財産管理の制度と言えば、成年後見制度、任意後見制度などがありますが、いずれも、資産を減らさないようにするための管理しかできず、資産を運用する形での管理はできません。
家族信託ならば、成年後見制度、任意後見制度に比べて、柔軟な財産管理を行うことができるので、注目されています。
家族信託と民事信託の違い
家族信託は、民事信託とも呼ばれます。
家族信託と民事信託は、実質的に同じ意味で違いはありません。このコラムでは、家族信託に統一して解説します。
家族信託の仕組み
家族信託では、3人の人物が関わります。
- 委託者
- 受託者
- 受益者
です。
委託者とは、信託をする人、つまり、信託したい財産を持っている人のことを意味します。信託したい財産は信託契約により、信託財産になります。
受託者とは、信託財産の管理や処分等を行う人のことです。
受益者とは、受託者が行う信託財産の管理や処分によって、利益を得る人のことです。
家族信託は、高齢の親が多額の財産を持っている場合に、自分の財産を子どもに管理してもらう目的で設定されることが多いです。
このケースでは、委託者、受託者、受益者はそれぞれ次のような関係になります。
- 委託者:高齢の親
- 受託者:子ども
- 受益者:高齢の親
家族信託のメリット
家族信託を利用した場合の主なメリットを紹介していきます。
柔軟な財産管理が可能
家族信託は、高齢の親の財産を管理するための制度として利用されています。
財産管理が目的でしたら、成年後見制度等を利用することも可能です。
ただ、成年後見制度や任意後見制度は、使い勝手が良い制度ではありません。
毎年、家庭裁判所への報告義務がありますし、後見人に専門家が選ばれた場合は、報酬の支払いが必要です。
さらに、現状の財産を減らさないための管理ができるだけで、財産を投資に回すといった積極的な運用は難しいです。
これに対して、家族信託なら子どもなどの家族が受託者となれば報酬は必要ありませんし、家庭裁判所への報告といった煩わしい手続きも必要ありません。
更に、積極的な信託財産の資産運用をすることが可能ですし、信託財産が多額で相続時に多額の相続税の発生が懸念されるケースでは、信託財産を減らしたり、財産の組み換えにより節税を試みることもできます。
二次相続の指定ができる
自分の財産の相続方法を指定するには、遺言書を書き残すのが一般的な方法です。
遺言書は、自分の財産を、特定の誰かに引き継ぐことはできますが、その人からさらに他の人に承継させることについては指定することができません。
例えば、自分の財産を長男に引き継がせた後で、長男には子どもがいないため、その次は次男の子ども(孫)に引き継がせたいと考えていたとします。
遺言書では、自分の財産を長男に相続させることまではできますが、長男に対して、次は次男の子ども(孫)に相続させるように指示することはできません。
付言事項として、「次男の子ども(孫)に相続させてほしい」と願いを書き残すことはできますが、その願いを聞き入れるかどうかは、長男次第です。長男が何もしなければ、長男の配偶者に遺産が渡り、次男の子ども(孫)に引き継がれない可能性があります。
一方、家族信託なら、設計次第で二次相続の指定も可能です。
まず、受益者が死亡すると信託財産は帰属権利者に引き継がれます。
例えば、
- 委託者:高齢の親
- 受託者:子ども
- 受益者:高齢の親
- 帰属権利者:子ども
このように設定した場合は、高齢の親が生存中は、その親の生活費や介護費用を捻出するために信託財産を管理運営して、その親が亡くなったら、子どもが残りの信託財産を相続できます。
そして、受益者は一人だけではなく、二人以上に設定することもできます。
例えば、高齢の父親と母親のために家族信託を利用するケースであれば、第1受益者を父親、第2受益者を母親とすることで、父親が亡くなった後、引き続き、母親のために信託財産を管理ししてもらうことが可能です。
- 委託者:高齢の親
- 受託者:子ども
- 第1受益者 :高齢の父親
- 第2受益者 :高齢の母親
- 帰属権利者:子ども
この仕組みを利用して、次のような設定にすると、二次相続の指定も可能になります。
- 委託者 :高齢の親
- 受託者 :次男
- 第1受益者 :高齢の親
- 第2受益者 :長男
- 帰属権利者 :次男の子ども(孫)
このようにしておけば、長男は信託財産の受益者に過ぎず、最終的に次男の子ども(孫)に遺産を相続させることができるわけです。
障害がある子どもに財産を残せる
子どもに障害があり、一人で生活することが難しい場合は、自分の死後、子どもがどうなるか不安でしょう。
家族信託の利用により、障害がある子どもに財産を残すことができます。
例えば、
- 委託者:高齢の親
- 受託者:健常者の子ども
- 受益者:障害がある子ども
このような形で信託を設定しておけば、自分の遺産を障害がある子どものために使ってもらうことも可能です。
相続で不動産を共有した場合に1人に管理を任せられる
相続財産の中に不動産がある場合は、換価分割、現物分割、代償分割によって、相続人の誰か一人の所有とするのが望ましいとされています。
しかし、その不動産が賃料収入を生み続ける賃貸マンションなどの賃貸物件の場合は、誰が相続するか決まらず、共有とすることもあるかもしれません。
このような場合は、共有者の中で賃貸物件を管理運営する人を一名決めて、他の共有者から信託するという形を取ることで、賃貸物件の管理運営を一元化することも可能です。
賃貸物件を共有している場合、契約や大規模修繕では、共有者全員の同意等が必要になることがありますが、一人でも、同意できない人がいると、管理運営が滞ってしまいます。
家族信託を利用して一人に賃貸物件の管理運営を任せれば、そのようなリスクを最小限に抑えられます。
相続時に遺産分割協議が必要ない
相続時の遺産分割協議は、相続人にとって大変な負担になることがあります。
相続人同士が遠方に住んでいる場合は、話し合いを行うことが難しいこともありますし、遺産をめぐってトラブルに発展することもあります。
家族信託を利用した場合、受益者が亡くなった際は、帰属権利者が自動的に信託財産を相続することになるので、遺産分割協議を行う必要はありません。
家族信託のデメリット
家族信託は、高齢の親の多額の財産管理や相続の問題を解決するための万能の手段ではありません。いくつかのデメリットがあるので紹介していきます。
身上監護は行うことができない
家族信託では、受託者に信託財産の管理を任せることはできますが、受益者の身上監護については、受託者に依頼することはできません。
そのため、介護施設などへ入居する際は、本人が契約を行わなければなりません。その契約も第三者に依頼したい場合は、任意後見契約の利用を検討すべきです。
なお、介護施設への入居費用の支払いだけであれば、家族信託により、受託者が信託財産の中から支払うこともできます。
受託者が決まらないこともある
家族信託を利用する時は、家族や親族などの誰かが受託者として信託財産の管理をします。
しかし、信託財産の管理は手間が掛かりますし、責任も伴います。
そのため、受託者になってくれる家族や親族が決まらないこともあります。
相続人同士で不公平感が生じることがある
家族信託を設定しているときに相続が発生した場合、相続人間で不公平感が生じるケースがあります。
家族信託により、高齢の親の財産管理を子どもの一人が担っている場合なら、受託者となったその子どもは信託財産を比較的自由に使うことができます。
そのため、受託者による信託財産の使い込みなどの問題が生じるケースがあります。
また、子どもの一人を信託財産の帰属権利者とし、他の子どもには相続する遺産がない状態になると、やはり、相続争いの原因になってしまうこともあります。
信託財産が相続に際して、受託者などに帰属することになった場合は、その財産も遺留分侵害額請求の対象となるからです。
相続税の節税になるわけではない
家族信託を利用すると、生前に相続人に遺産を渡すことができると言われています。
例えば、不動産を所有している高齢の親が家族信託を利用して、子どもにその不動産の管理を委ねたとします。
この場合、不動産の登記名義は親から子どもに移転します。
受託者となった子どもは、自分名義の財産としてその不動産を管理できるわけです。生前贈与とは違うのでこの時点では、贈与税や相続税は発生しません。
ただ、親が亡くなり、子どもがその不動産の帰属権利者となった場合は、その時点で、相続税と同様の税額を納付しなければなりません。
そのため、相続税の直接的な節税にはならないわけです。
家族信託を利用するのに必要な手続き
家族信託を利用する際の大まかな手続きは次のとおりです。
- 家族信託を利用することについて家族で話し合う
- 信託契約を締結し契約書を作成する
- 信託口座の開設、信託登記を行う
- 信託財産の管理や運用を始める
一つ一つ確認しましょう。
家族信託を利用することについて家族で話し合う
家族信託を利用する際は、まず、家族の間で話し合うのが基本です。
まず、家族信託を利用する目的を確認します。
親の財産の管理が目的なのか、二次相続対策を見据えているのか、相続税対策として利用するのかといったことです。
次に受託者となる人を慎重に選定します。
受託者による信託財産の管理権限は大きいので、家族の中でも信頼できる人物を選ばなければなりません。
ケースによっては、受託者が適切に信託財産の管理運営を行っているか、監督する「信託監督人」を選任すべきこともあります。信託監督人の資格は特に決まりはありませんが、弁護士などの専門家に依頼することも多いです。
信託契約を締結し契約書を作成する
家族信託に関して取り決めた内容について、契約書にまとめます。
契約書は当事者同士が任意に作成する私文書による方法と、公証人に依頼して作成してもらう公正証書による方法があります。
私文書の場合は、ひな形を参考に作成することも可能ですが、信託内容に関して後で争いが生じることもあります。
高額な財産に関して家族信託を行いたい場合は、信託契約書を公正証書で作成するのが無難です。
信託口座の開設、信託登記を行う
家族信託で銀行預金を管理するケースでは、信託口座を開設します。
信託口座とは、受託者が自分の個人的な預金と分離して信託財産の管理をするための口座です。
信託口座の開設のためには、公正証書による信託契約書を用意しなければならないのが一般的です。
信託登記は、不動産を信託財産とする場合に行います。
家族信託を利用すると不動産の所有権登記名義人は、受託者に移転します。これだけでは、売買や相続により所有権移転登記がなされた場合と見分けがつきませんので、信託による移転である旨の特別な登記を行います。
その登記のことを信託登記と言います。
信託登記については、一般の相続登記よりも難易度が高いため、司法書士、または信託に詳しい弁護士にご相談ください。
信託財産の管理や運用を始める
以上の手続きが終われば、信託財産の管理や運用を始めることができます。
成年後見制度を利用する際は、家庭裁判所での審判や手続きが必要になりますが、家族信託ならこうした手間が掛からず、速やかに信託財産の管理や運用を始められる点が利点です。
家族信託した財産に関して相続が発生する場合
家族信託した財産に関して相続が発生するのは、「受益者」が亡くなった場合です。
「委託者」が亡くなった場合は、原則として委託者の地位が「委託者」の相続人へ引き継がれますが、これに関しては特に意味はありません。
「受託者」が亡くなったケースでは、信託財産を管理する人がいなくなったことになるため、新たな「受託者」を決めなければなりません。
基本的に「受託者」の相続人は「受託者」の地位を引き継ぎません。1年以内に新たな「受託者」が決まらない場合は、家族信託自体が終了します。
受益者が亡くなった際の相続手続き
受益者が亡くなった時は、家族信託した財産について相続手続きが必要になることがあります。
受益者が亡くなった時は、受益者の相続人が受益を受ける権利を相続するのが原則です。
ただ、受益者が亡くなった際に、次のいずれかの対応を採る旨が定められているのが一般的です。
- 受益者の死亡により信託契約を終了させる
- 受益権を引き継ぐ人を決めておく(受益者連続信託)
例えば、高齢の親の財産管理を主な目的として家族信託を設定した場合なら、親が亡くなれば、家族信託の役割は終わりますから、信託契約を終了させるのが一般的です。
残された信託財産については、帰属権利者が相続します。
一方、二次相続対策を目的に家族信託を設定した場合なら、第一の受益者が亡くなった際には、第二の受益者に引き継ぐ旨を定めておきます。受益者連続信託と呼ばれる方法です。
この場合は、相続手続きを行う必要はありません。
なお、受益者連続信託を利用するケースでも、第二の受益者が引き継ぐ時点で相続税が課税されるので注意しましょう。
まとめ
家族信託の相続における活用方法、メリットやデメリットを解説しました。
家族信託は、高齢の親の財産管理だけでなく、生前の相続対策や二次相続対策としても有効な方法です。
ただ、家族信託の仕組みが分かりづらいことから、利用をためらっている方も多いのではないでしょうか。
家族信託に関して分からないことがある時や、トラブルが発生した時は、弁護士等の専門家にご相談ください。