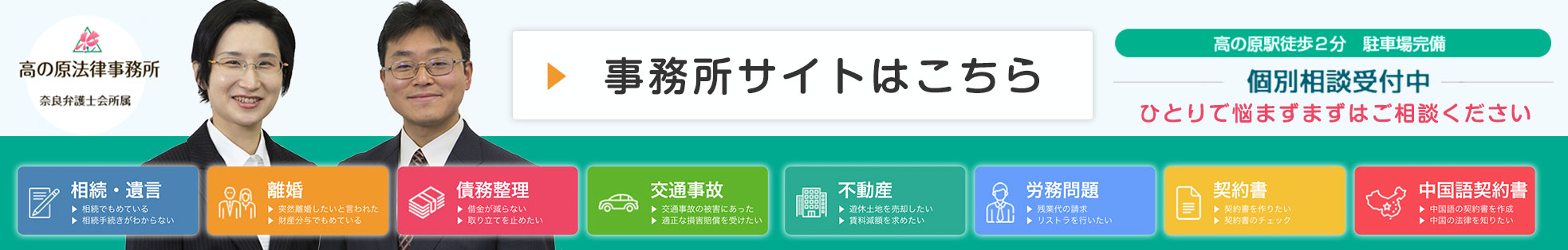コラム
法定相続人になれる範囲はどこまで?順位や割合を弁護士が解説!
相続が発生したけれど「誰が法定相続人になるのかわからない」「法定相続人はどこまで?」「もめたらどうしよう」と不安に思う方は多いです。
本記事では、法定相続人の順位や相続分、法定相続人についてよくある疑問などに弁護士が丁寧に解説します。
相続が発生したとき、「法定相続人になれる人はどこまでなのだろう」と不安になる方は多いです。
親族との関係をよく知っているつもりでも、法律上の相続権は思わぬ範囲におよぶことがあります。
法定相続人を間違えて認識してしまうと、遺産分割協議が成立せず、後々大きなトラブルに発展するリスクもあるでしょう。
本記事は、法定相続人の範囲や優先順位、各相続人の取り分について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
誰がどのように相続するのかがわかり、相続手続きをスムーズにすすめるための正しい知識を得られます。
法定相続人のルールを理解すれば、相続トラブルを未然に防げるかもしれません。
法定相続人とは?
法定相続人は、民法で定められる「遺産を受け取る権利のある人」のことです。
被相続人との関係に応じて、法律上認められる一定の人だけが相続人となります。
配偶者は常に法定相続人であり、これに加えて、血族の中から優先順位に応じたグループが選ばれる仕組みです。
身近な例でいえば、配偶者と子が一緒に相続人になるケースが多いです。
法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。
このうち血族相続人は順位に応じて決まり、配偶者とは常に共同で相続人となるルールです。
血族相続人については、①直系卑属②直系尊属③兄弟姉妹の順で、順位の高い人が優先されます。
たとえば、子がいる場合に親や兄弟姉妹へは相続権が生じません。
こうしたルールにより、誰がどのくらい相続するか整理されており、民法900条では法定相続分という遺産の取り分が細かく定められています。
以下の表で、代表的なパターンごとの法定相続分をまとめています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1(子全体で) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1(直系尊属全体で) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(兄弟姉妹全体で) |
もし遺言がなければ、原則としてこの割合に従って遺産分割が行われます。
法定相続人とはどこまでの範囲?
すでに上述したとおり、法定相続人における優先順位の一覧は次のとおりです。
- 常に法定相続人:配偶者
- 第1順位:直系卑属
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
各法定相続人に誰が該当するのか、どういった背景で上記の順位となっているのかそれぞれ具体的に解説していきますね。
常に法定相続人:配偶者もつのが配偶者です
結婚している限り、夫または妻は常に相続人となります。
直系卑属や直系尊属などがいるかにかかわらず、配偶者は法定相続分を確保できる立場です。
配偶者が単独で相続する場合もあれば、他の相続人と一緒に財産をわけ合うこともあります。
遺産分割協議でも配偶者の立場は重要です。
家計を支え合ったパートナーとして、生活の安定を重視する法律の趣旨が背景にあります。
第1順位:直系卑属
被相続人の子や孫が、最も優先される第1順位の相続人です。
直系卑属には、血縁関係にある子どもが含まれます。
子がすでに亡くなっている場合、その子の子、つまり孫が代わりに相続します。
この仕組みが代襲相続です。
直系卑属がいると、直系尊属や兄弟姉妹へは相続権が移りません。
家族の財産を次世代へ引き継ぐことを大切にする考え方が根底にあります。
第2順位:直系尊属
直系卑属がいない場合、親や祖父母などの直系尊属は第2順位の相続人です。
父母が健在ならば、基本的に両親が相続人にあたります。
もし両親も他界しているならば、祖父母が相続権をもつことになります。
直系尊属が相続するケースは比較的少ないでしょう。
しかし、直系尊属は相続人として法律上しっかりと位置づけられています。
親の生活を支えるという意味もあり、こうした制度が設けられています。
第3順位:兄弟姉妹
直系卑属と直系尊属がいないとき、兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
兄弟姉妹は基本的に平等な割合で遺産をわけ合うことになります。
ただし、すでに亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる場合、その子(甥や姪)が代襲相続します。
兄弟姉妹の立場での相続は、直系親族に比べて優先度が低いものの、身内として財産を受け継ぐ権利が法律で認められているのです。
法定相続人を調査する方法
法定相続人の情報を正確に把握するには、戸籍関係の書類確認が必要です。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどれば、誰が法定相続人にあたるかを明らかにできます。
具体的には、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「除籍謄本」「原戸籍」などです。
たとえば、除籍謄本は、すでに全員が除籍された戸籍の記録を証明するもので、重要な手がかりとなります。
これらの書類は、本籍地の市区町村役場で入手するのが基本です。
現在住んでいる場所と異なる場合も多いため、注意が必要です。
自治体によっては郵送や電子申請、コンビニ交付が可能な場合もあります。
法定相続人なれないケース
法定相続人がどこまでかという範囲とその優先順位や、その確認方法について解説してきましたが、たとえこの範囲の人であっても、制度によって相続人になれないケースも存在します。
相続人になれなくなる制度は下記の場合です。
- 相続放棄
- 相続欠格
- 相続廃除
それぞれの制度について解説します。
相続放棄
相続人が相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったものと扱われます。
裁判所へ申立を行い、正式に認められると、相続権を完全に失うことになります。
この場合、放棄をした人の子どもが代わりに相続することも認められていません。
たとえば、借金を多く抱えている被相続人の財産を引き継ぎたくないときなどに使われます。
リスク回避のための有効な手段といえます。
相続欠格
重大な非行を行った相続人は、相続欠格となり、自動的に相続権を失う決まりがあります。
たとえば、被相続人を故意に死なせた場合や、遺言書を偽造・隠匿した場合などが該当します。
欠格にあたる行為をした本人だけが相続権を失うため、その子どもには影響がおよびません。
法律は相続の秩序を守るため、一定の厳しい制裁を設けています。
相続廃除
推定相続人に著しい非行や虐待があったとき、相続廃除によって相続権を失わせることが可能です。
これは被相続人の申立に基づき、家庭裁判所が認めた場合に成立します。
たとえば、著しい暴力や人格を否定するような侮辱行為などが対象です。
廃除された本人は相続人になれませんが、その子どもは代わりに相続人になれます。
家族関係の信頼を守るための制度です。
法定相続人がどこまでかについてよくある疑問
法定相続人についてはどこまでの範囲なのかに関して、よくある質問が下記の内容です。
- 事実婚・内縁関係のパートナーは法定相続になれないのか?
- 養子は法定相続人か?
- 離婚した元配偶者は法定相続人か?
- 再婚相手の連れ子は法定相続人か?
- 法定相続人がいないケースはどうなるのか?
- 遺言書がある場合、法定相続人はどのように扱われる?
それぞれの疑問について回答していきますね。
事実婚・内縁関係のパートナーは法定相続になれないのか?
法律上の婚姻届を出していない事実婚・内縁関係のパートナーには、法定相続権が認められていません。
たとえ長年一緒に暮らし、生活を共にしていても、法律で「配偶者」と認める基準に達していないからです。
遺言によって財産を譲る方法は可能ですが、遺言がない場合、内縁の配偶者は遺産を受け取ることはできません。
トラブルを防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談して早めに対策を考えることが重要です。
養子は法定相続人か?
養子は、実子と同じく法定相続人です。
養子縁組が成立していれば、血のつながりがなくても相続権をもつことになります。
たとえば、子どものいない夫婦が養子を迎えた場合、その養子は自然な形で相続に参加できます。
ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では一部取り扱いに違いがあるため、注意が必要です。
離婚した元配偶者は法定相続人か?
離婚した元配偶者は、相続人にはなりません。
婚姻関係が解消されると、民法上の配偶者ではなくなるため、相続権も消滅します。
仮に、離婚後も親しい関係が続いていても、法律上の保護は受けられない仕組みです。
財産を渡したい場合は、遺言による指定が必要です。
再婚相手の連れ子は法定相続人か?
再婚相手の連れ子は、法律上法定相続人にはなりません。
血のつながりがないため、養子縁組をしていない限り、相続権をもつことはできない仕組みです。
連れ子にも相続させたい場合には、正式に養子縁組が必要です。
法定相続人がいないケースはどうなるのか?
法定相続人がまったくいない場合、最終的に遺産は国庫に帰属する仕組みです。
たとえば、配偶者も子どももおらず、親兄弟もすでに亡くなっているケースでは、財産を引き継ぐ人がいないと判断されます。
この場合、特別縁故者と呼ばれる関係者が家庭裁判所に申立を行い、認められれば遺産を受け取れる可能性もあります。
ただし、申立がない場合にはすべて国のものです。
遺言書がある場合、法定相続人はどのように扱われる?
遺言書が存在する場合、基本的にはその内容に沿って財産が分配されます。
たとえば、遺言書で特定の人に遺産を渡すと指定される場合、法定相続人だとしても遺産を受け取れないこともあるでしょう。
ただし、法定相続人には最低限の取り分である遺留分が認められています。
遺留分を侵害された場合、相続人は取り戻すための請求が可能です。
遺言書があるからといって、すべて遺言書どおりになるわけではありません。
法定相続人について迷った際は弁護士にご相談を
法定相続人について迷った際は、弁護士に相談することをおすすめします。
相続問題については、法定相続人が誰かはもちろん重要ですが、遺言書や財産調査など複数の問題が複雑に絡みやすいです。
弁護士に相談しておくことで、後のトラブルを防止できます。
弁護士に依頼する主なメリットは次のとおりです。
- 法定相続人を正確に把握できる
- 相続問題・遺産分割問題に法的に対応してもらえる
それぞれ解説していきますね。
法定相続人を正確に把握できる
相続手続きでは、法定相続人を正確に特定することが非常に大切です。
戸籍をたどっていくと、予想外の相続人が判明することも珍しくありません。
親族だから把握しているつもりでも、実際には見落としがあるケースは多く見受けられます。
専門の弁護士に依頼すれば、正確な戸籍調査と法律知識に基づき、相続人を確定できます。
安心して遺産分割協議をすすめるためにも、専門家の力を借りることが大事です。
相続問題・遺産分割問題に法的に対応してもらえる
相続に関する問題は、親族間だけでは解決が難しいことも少なくありません。
誰が相続人か、どこまでが相続財産かをめぐって争いが起きやすいからです。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、相続人調査や財産調査をスムーズにすすめられます。
さらに、遺産分割協議がもめた場合でも、法律に基づいた適切な対応が期待できます。
まとめ
この記事では、法定相続人がどこまでなのかという範囲や優先順位、各相続人の取り分について解説してきました。
記事のポイントは下記のとおりです。
- 配偶者は常に法定相続人であり、子や親、兄弟姉妹は順位で決まる
- 子がいないケースは直系尊属、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になる
- 法定相続分は配偶者と子で2分の1ずつ、直系尊属なら配偶者が3分の2
- 法定相続人を調査するには出生から死亡までの戸籍一式が必要
- 相続放棄や相続欠格、相続廃除で本来の相続人が権利を失うことがある
法定相続人の範囲は、単なる親しさや交流だけで決まるものではありません。
法律に基づき、きちんと順位と割合が整理されています。
相続問題は小さな誤解が後の大きなトラブルにつながりやすいので、正しい知識がとても大切です。
もし相続で迷ったときは、早めに弁護士などの専門家へ相談する行動が未来を守ります。
法律事務所によっては無料で相談できるところもありますよ。