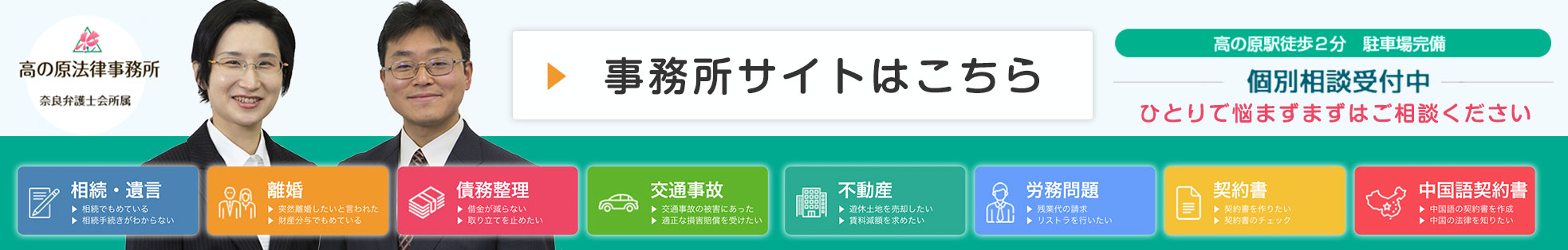コラム
相続で介護について寄与分が認められるケースとは? 証拠の集め方や計算方法も解説
相続人である子どもが親など被相続人の介護を担当し、その貢献度が高いケースでは、相続の際に寄与分が認められることもあります。しかし、親子の扶養義務の範囲と判断されて寄与と認められないことも多くあります。介護について相続時に寄与分を主張するための証拠の集め方等を解説します。
相続で介護の寄与分を認めてもらうには? 証拠の集め方も解説
相続が発生した際は、被相続人の介護を担っていた相続人には寄与分が認められて、他の相続人よりも取り分を多くしてもらえることがあります。
しかし、介護をしていれば必ず寄与分が認められるわけではなく、介護サービスを利用しながら、仕事やプライベートと両立させていたケースだと、認められないことがほとんどです。
寄与分をめぐって、介護を担当していた相続人とそうではない相続人とで対立が生じることも少なくなく、相続トラブルの原因にもなりがちです。
この記事では、相続において介護の寄与分が認められるケースや証拠の集め方、遺産分割での主張方法について解説します。
介護をしていた場合に認められる相続人の寄与分とは?
相続人の中で、被相続人の介護のために貢献した人がいるケースでは、相続財産の中から寄与分が認められるので、他の相続人よりも相続財産の取り分が多くなることがあります。
この場合、介護を担っていた相続人への寄与分について計算を行い、その分を相続財産から除外します。
その後、残りの相続財産につき、法定相続分で分け合うという形になります。
例えば、親が1800万円の遺産を残して亡くなり、法定相続人が子ども3人だったとします。
通常の法定相続分で計算すると、子ども3人がそれぞれ600万円ずつ遺産を分け合う形になるのが原則です。
しかし、子どものうち、長女が親の介護を長年献身的に担っており、その寄与分が300万円相当と認定されたとしましょう。
この場合は、上記のように原則の法定相続分では、長女にとって不公平です。
そこでまず、長女の寄与分300万円を遺産の中から引きます。
そして、残りの1500万円を長女も含めた子ども3人がそれぞれ500万円ずつ遺産を分け合う形になります。
その結果、長女の取り分は、
寄与分300万円+500万円=800万円といった計算になるわけです。
このように被相続人の介護を献身的に担っていた相続人がいるケースでは、遺産相続において、その貢献に報いるために、寄与分の制度が用意されています。
介護を担う相続人は増えている
今日では超高齢社会になり、平均寿命も伸び続けています。
令和6年版高齢社会白書によると、令和元年(2019年)の平均寿命は、男性で81.41歳、女性で87.45歳となっています。
一方で、健康的に日常生活を送ることができる健康寿命は、男性では72.68歳、女性では75.38歳となっています。
つまり、後期高齢者になると多くの方が日常生活で介護や支援が必要になる可能性があります。
男性では亡くなるまでの9年間、女性では12年間にわたり、介護が必要になる可能性があります。
そして、相続人が介護の担い手となることも少なくありません。
通常の介護をしただけでは相続人に寄与分が認められない?
相続人が介護をしていれば、必ず寄与分が認められるわけではありません。
むしろ、介護をしていたにも拘らず、寄与分を請求できないというケースの方が多いのが実情です。
その理由は、「子どもが親の介護をするのは当然」という考え方が今でも根強いからです。
また、民法でも、親族間の扶養義務について規定した条文がいくつかあります。
民法730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法ではこのように、親族や家族間の扶養義務について念入りに規定しています。
この扶養義務には、相続人である子どもが親を介護することや配偶者が他方の配偶者を介護することも含まれます。
そして、この扶養義務の見返りについては特に規定は設けられていません。
そのため、通常の介護の範囲に留まるなら、寄与分は発生しないのが一般的です。
相続において寄与分として認められる介護の程度とは?
では、介護を理由とする寄与分はどのような場合に発生するのでしょうか?
この点については、民法904条の2に規定が設けられています。
「被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」
つまり、「特別の寄与」と言えるほどの貢献をした場合に限って、寄与分が認められるということです。
例えば、親の介護のために、様々な介護サービスを利用する際は、親の財産からその費用を出すのが一般的です。
もちろん、介護費用を出せば、その分、親の財産が減りますし、亡くなった際の遺産も減ります。
一方、相続人である子どもが自分のお金から親の介護費用を出していたのであれば、親の財産は減りませんし、亡くなった際にその分遺産が多く残ります。
このような場合は、相続人である子どもは親の介護費用相当額につき、寄与分を主張できます。
親の介護を特定の子どもだけが担っていた場合でも、介護費用は親のお金から出していたというケースでは、子どもとして当然の扶養義務を果たしていただけと判断されやすく、寄与分が認められにくいのが実情です。
特別の寄与として考慮される程度の介護とは?
介護を担う相続人の貢献度が特別の寄与と言えるかどうかは、ケースバイケースです。
特別の寄与として考慮されやすいケースをいくつか紹介します。
無償で介護に関わっていた場合
被相続人の介護を相続人が無償で行っていた場合です。
無償とは、被相続人からお小遣いをもらっていたとか、生前贈与を受けていたといった事情がないという意味です。
被相続人の介護を担う代わりに、被相続人から何らかの見返りを得ていた場合は、報われていることになるため、特別の寄与に当たらない可能性があります。
介護が長期間続いた場合
被相続人の介護を相続人が担っていた期間が普通よりも長い場合です。
何年間介護をしていれば、特別の寄与に該当するという明確な線引はありません。
判例でも25年、37年など、いろいろな数字が上がっていますが、介護期間の長さは考慮要素の一つに過ぎず、他にも様々な事情が考慮されます。
介護に専従していた場合
介護離職するなど、介護のために自分の生活をある程度犠牲にしていた場合です。
介護と自分の生活や仕事を両立させていたケースでも、介護を担うことは大変な負担ですが、その程度なら扶養義務の範囲と判断されやすいです。
介護の際に被相続人の財産を減らしていないこと
特定の相続人が介護してくれたおかげで、被相続人を老人ホームなどに入居させずに済ませられた。そして、費用が浮いた分、多めに遺産が残った場合です。
- 被相続人の状態が要介護状態で、通常なら、老人ホームなどへの入居が必要だったこと。
- 老人ホームへ入居せずに特定の相続人が被相続人を介護したことで浮いた費用の具体額。
これらを主張、立証することで、寄与分が認められやすくなります。
相続で介護による寄与分を主張するための証拠とは?
相続後の遺産分割協議において介護による寄与分を認めてもらうには、証拠、裏付け資料が必要です。
遺産分割協議の場では、
「私が被相続人の生前に介護をしていたことは、他の相続人も知っているはず。だったら、寄与分が認められて当然だ。遺産相続も多くもらえるはずだ」
といった感情的な主張をしたくなるかもしれません。
しかし、相続人同士で話し合いがまとまらず、家庭裁判所の遺産分割調停の場に持ち込まれた場合は、事情を知らない調停委員に介護を担っていた事実やその介護を行ったことが特別の寄与に当たる旨を主張する必要があります。
そのためには、口で説明するだけでなく、裏付けとなる証拠が必要なのです。
介護による寄与分を主張するための裏付け資料は次のとおりです。
- 介護が必要な状態だったことの資料
- 介護サービスを利用していたことの資料
- 自分が介護を担っていたことを示す資料
一つ一つ確認しましょう。
介護が必要な状態だったことの資料
一般的には、要介護認定通知書などです。
要介護認定通知書は、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5という段階に分かれていますが、概ね、「要介護2」以上が介護が必要なラインになります。
また、要介護認定の後で、ケアマネジャーが作成したケアプランも、どの程度の介護が必要なのか知る資料となりえます。
相続人が自宅で被相続人を介護していた場合は、要介護認定を受けていないケースもあります。このような場合は、医師の診断書などが有力な証拠になります。
介護サービスを利用していたことの資料
一般的には、介護サービスを利用する際の契約書です。
介護サービスにかかる費用の支払いは、銀行口座からの引き落としが一般的なので、その口座の取引履歴を用意します。
相続人の口座から支払っていたのであれば、その支払い分が寄与分に該当するものと認められやすいです。
自分が介護を担っていたことを示す資料
相続人が、被相続人の生前に介護していたことを客観的に示す公的な資料はありません。
要介護認定を受けても、介護サービスを利用していなかった場合なら、同居の家族が介護していたと推定できますが、具体的に誰が介護を行っていたのかは、それだけでは分かりません。
この場合は、介護を担当している相続人が、詳細な介護日誌をつけておくと有効です。
介護日誌を書く際は、「5W1H(誰が・何を・いつ・どこで・なぜ・どのように)」を意識して具体的な内容を書くことが大切です。
介護の作業だけでなく家事も手伝っていたなら、そのことも書きましょう。
例えば、「今日はおむつを2回替えた」という記述だけでは、誰がそれをやったのか分かりません。介護を担当している相続人が自分でその介護を行ったということが分かるように記載しましょう。
相続人以外の人が介護による寄与分を主張するには?
寄与分は法定相続人だけに認められている権利ですが、相続人以外の人でも、被相続人の介護を担っており、特別の寄与をしたと認められれば、特別寄与者として寄与分を請求することができます(民法1050条)。
介護による特別寄与があったと認められるのは、次の要件を満たしている場合です。
- 被相続人の親族であること。
- 無償で療養看護を行い、特別の寄与をしたと言えること。
- 相続開始後相続人が確定してから6か月以内又は相続開始から1年以内に主張していること。
被相続人の親族というのは、民法725条の親族の範囲に含まれる人たちのことです。
具体的には、
- 六親等内の血族
- 配偶者
- 三親等内の姻族
のいずれかです。
例えば、被相続人の長男の嫁は、法定相続人ではありませんが、被相続人から見て三親等内の姻族に該当します。
そのため、長男の嫁が義父母の介護を無償で担っていたケースでは、特別寄与を主張できる立場になります。
特別寄与の程度については、相続人による寄与の程度と同じと考えられています。
そして、注意点は、特別寄与を主張できる期間が限られていることです。
一般的には、被相続人が亡くなってから6か月以内に、特別寄与の主張をしておかないと、以後は主張できなくなるので注意しましょう。
相続において介護による寄与分を認めてもらうには?
相続手続きにおいて、介護の寄与分を認めてもらいたい場合は、相続人が自ら主張しなければなりません。親族による特別寄与の主張も同様です。
相続手続きで介護の寄与分を主張できるチャンスは次の3つです。
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
遺産分割で主張する際の流れを一つ一つ確認しましょう。
遺産分割協議
遺産分割協議とは何かというと、被相続人が亡くなった後で、相続人の遺産をどのように分け合うかについて、相続人同士で話し合うことです。
葬儀が終わり、49日が過ぎてある程度落ち着いてからこうした話し合いの場が設けられることが多いでしょう。
この話し合いの場で、介護の寄与分を主張したいなら、しっかりと主張することが大切です。
介護による寄与分を主張する際のポイントは、「介護を担っていたんだから遺産を多く貰えて当然」といった漠然とした主張を行うのではなく、裏付け資料を基に具体的な金額を示すことです。
他の相続人が納得できる数字を示せば、その金額が寄与分として考慮されて、遺産の中から先に取得することができます。
遺産分割調停
相続人だけで遺産分割協議を行っても埒が明かない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。
遺産分割調停では、相続人同士が直に顔を合わせて話し合うわけではなく、調停委員が間に入って、相続人一人ひとりから話を聞く形が取られるのが一般的です。
寄与分の主張についても調停委員に対して行います。
調停委員は、相続人同士の事情や介護の事情については全く知らない第三者ですから、介護による寄与分は裏付け資料に基づいて説明しないと、理解してもらいにくいです。
遺産分割調停になった場合は、裏付け資料を整理して有効な主張を行うことが大切です。
遺産分割審判
遺産分割調停は相続人全員が納得しなければ、調停不成立となってしまいます。
この場合は、自動的に家庭裁判所の裁判官による審判という形になります。
審判は、裁判と似た形式で行われるため、自分の主張は証拠に基づいて行う必要があります。
やはり、裏付け資料を整理して有効な主張を行うことが大切です。
相続で介護による寄与分を主張するなら弁護士に依頼することも検討しよう
相続において介護による寄与分を主張するためには、客観的な証拠が必要ですし、法的に意味のある主張を行うことが大切です。
特に、遺産分割調停や遺産分割審判の場では、その点が重要になります。
裏付け資料は用意できても、それを基にどう主張すればいいのか、具体的な金額はどのように計算したらよいか、解決する方法がわからないこともあると思います。
このような場合は、弁護士に相談してください。
遺産分割協議の段階でも、弁護士に相談して、具体的な寄与分の額を計算してもらえば、他の相続人にも、その金額を主張しやすくなりますし、揉め事にならずにスムーズに遺産分割協議を終えられることもあります。