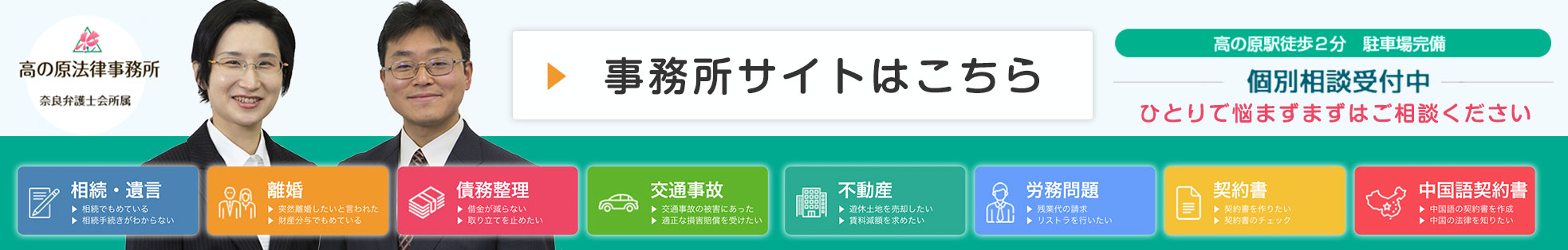コラム
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは? 相続トラブル回避のポイントも解説
公正証書遺言は公証人に作成したもらうもので、法的に無効になるリスクが低いというメリットがあります。自筆証書遺言は、証人の立ち合いが必要なく費用もかからず、すぐに作成できる点がメリットです。
一方で、両方の遺言にはそれぞれデメリットもあります。
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばいいのか? 相続トラブル回避のポイントも解説します。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは? それぞれのメリットとデメリットも解説
遺言には、大きく公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言は公証人に作成してもらうもので、法的に無効になるリスクが低い遺言です。自筆証書遺言は自分で作成する遺言なので有効な遺言にするためには、民法の規定を遵守する必要があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言のそれぞれのメリットとデメリットや作成方法について解説します。
遺言とは何か?
遺言とは、遺言を書いた人が亡くなった後で、遺言に書かれた内容を法的に実現することを保障する制度です。
個人は誰でも、自分の死後に自分の財産をどのように処分したいのかについて、自由に決めることができます。
そのためには、民法960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とあるとおり、一定のルールを守らなければなりません。
また、遺言によって実現できることも民法に規定されています。
もちろん、遺言で実現できない内容も書くことはできますが、こうした内容は、付言事項として、法的効力がないものとして扱われます。
遺言の方式とは?
遺言の方式とは、遺言書の種類のことです。
遺言の方式には、普通の方式と特別の方式があります。
普通の方式とは、一般的に作成する遺言のことで、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
特別の方式とは、やむを得ない状況の下で作成される遺言で次のような種類があります。
- 死亡の危急に迫った者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言
上記で紹介したように、遺言には様々な種類がありますが、一般的に作成される遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかであることが多いです。
自筆証書遺言は、遺言を書きたい人が紙に自筆で書くことによって作成する遺言です。
自由に書くことができますが、一定のルールを守らないと、無効になってしまうことがあります。
公正証書遺言は、自分が書き残したい内容を公証人に伝えて、公証人に作成してもらう遺言です。
作成方法については民法にルールが定められていますが、公証人が熟知しているため、法的に無効になる心配はありません。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で紙に書く遺言です。作成方法には次のようなルールがあります。
- 自筆で書く
- 財産目録以外は全て自書する
- 日付を自書する
- 氏名を自書する
- 印鑑を押す
- 文章を修正する際はルールに従う
一つ一つ解説します。
自筆で書く
筆記用具を使って紙に自分の手で書かなければなりません。
筆記用具や紙の種類については特に規定はありません。カーボン紙を用いて複写の形で記載された遺言書でも有効とした判例があります。
しかし、遺言書は長期間保管することが多いため、ボールペン等の容易に消えない筆記用具を使うことが望ましいです。
鉛筆では消えてしまう可能性があるので避けた方がよいです。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、さらに細かいルールがあります。
財産目録以外は全て自書する
自筆証書遺言は原則として全文を自書しなければなりません。
例外として、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その財産目録については、自書である必要はありません。
例えば、パソコンで一覧を作成したうえで、プリントアウトしたものでも構わないことになっています。
ただ、この場合は、プリントアウトした紙の一枚一枚に自書での署名と押印が必要になります。
日付を自書する
自筆証書遺言を作成したら、作成した日の日付を自書しなければなりません。
「令和7年9月15日」といった正確な日付を記載します。年号は、西暦と和暦のどちらでも構いません。
なお、「令和7年9月吉日」という記載は、日付の記載を欠くものとして無効になるとの判例があります。
氏名を自書する
自分の名前をフルネームで自書します。
財産目録をプリントアウトしている場合は、財産目録にも氏名を自書することを忘れないようにしましょう。
印鑑を押す
作成した遺言書に印鑑を押します。
なお、遺言書が数葉にわたる場合でも、日付、署名、押印は一葉にされていればよいとするのが判例です。
すべての遺言書を契印でつなげる必要はありません。
印鑑の種類については特に決まりはありません。
そのため、印鑑登録している印鑑を使う必要はありませんし、拇印(指印)でも構わないとするのが判例です。
印鑑を押す場所は一般的には氏名の近くですが、遺言書を封筒にしまっている場合において、封筒の封じ目に印鑑が押されていればよいとする判例もあります。
なお、財産目録をプリントアウトしている場合は、財産目録にも印鑑が必要なので注意しましょう。
文章を修正する際はルールに従う
文章を修正する際は、「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とされています。
具体的には、変更する箇所に二重線などを引いて、その近くに変更後の文言を書きます。
そして、変更した箇所に印鑑を押します。
更に、遺言書の隅に、「何文字削除、何文字追加 遺言者の氏名」と記載しなければなりません。
署名や印鑑を忘れてしまうこともあるので、間違えた場合は、すべて書き直すのが望ましいです。
なお、修正液などで修正することは認められていないので注意してください。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言は、法務局に預けることができます。自筆証書遺言書保管制度という制度です。
自筆証書遺言には、
- 遺言書を紛失してしまうおそれがある。
- 遺言書が改ざんされるリスクがある。
- 遺言書を発見してもらえない可能性がある。
- 相続開始後に家庭裁判所で検認を受けなければならない。
といった問題点があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで上記の問題点を解消することができます。
法務局に自筆証書遺言の原本を預けるので紛失や改ざんのおそれがありません。
また、遺言者が亡くなった後は、法務局が遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)や遺言者が指定した人への通知(指定者通知)を行ってくれるため、法務局に遺言書が保管されていることを相続人等に知ってもらうことができます。
さらに、遺言者が遺言書を預ける際に、法務局で確認を受けるため、家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。
こうしたメリットがあるので、自筆証書遺言書を作成した場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用するのが望ましいです。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の作成ルール
自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、民法のルールとは別に、法務局が定めたルールに則って自筆証書遺言を作成する必要があります。
具体的なルールを解説します。
用紙について
用紙は、A4サイズとされています。記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないものを用いましょう。
また、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を確保しなければなりません。
用紙については、法務局のサイトからダウンロードできるのでそちらを用いて書くのが無難です。
【参照】https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
記載方法
片面のみに記載します。
複数枚になる場合は、各ページにページ番号を記載します。その際は、総ページ数も分かるように記載します。
筆記具
筆記具は、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を用います。
遺言者の氏名
遺言者の氏名は、戸籍どおりの氏名を記載しなければなりません。
遺言書を保管する際に、公的書類等の添付資料で、申請人である遺言者本人の氏名を確認するためです。
ホッチキスで留めない
法務局に持っていく際は、ホッチキスで留めない状態で持っていきます。法務局で一枚一枚、スキャンしてデータを保存するためです。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言のメリットとデメリットを解説します。
まず、自筆証書遺言のメリットは次のとおりです。
- 費用が掛からない。
- 証人が必要ない。
- すぐに作成できる。
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば、今すぐに書き始めることができます。
万が一の場合に備えて、簡単な内容の遺言を書いておく際は、大変便利です。
子どもがいない夫婦の場合は、どちらか一方が亡くなった際は、兄弟姉妹が相続人となる可能性があり、夫婦の財産を兄弟姉妹に遺産分割しなければならないこともあります。
夫婦がお互いに、「すべての遺産を妻(夫)に相続させる」という趣旨の簡単な遺言書を書いておけば、こうした事態を避けることができます。
このように簡単な内容の遺言書を書く場合は、自筆証書遺言が最適と言えます。
自筆証書遺言のデメリットは次のとおりです。
- 遺言書の紛失のリスクがある
- 遺言書を発見してもらえない可能性がある
- 家庭裁判所の検認が必要
こうしたデメリットは、自筆証書遺言書保管制度でカバーできます。
それでも次のようなデメリットがあります。
- 遺言の内容が無効になるリスクがある。
- 遺言の内容によっては相続トラブルになるリスクがある。
自筆証書遺言書保管制度を利用しても、遺言の内容が有効か無効かの判断は法務局の担当者は行ってくれません。そのため、遺言の内容が無効になるリスクが残ります。
また、遺留分侵害の有無のチェックなども行ってもらえないので、相続トラブルになるリスクがあります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人に遺言したい内容を伝えて、公証人に作成してもらう遺言書です。
作成する際のルールとして民法には、次の2点が定められています。
- 証人二人以上の立会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
その他、作成方法などの細かいルールは、公証人が熟知しているため、遺言者が考慮する必要はありません。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言を作成する際の手順は次のとおりです。
- 財産目録を作成しておく。
- 遺言したい内容を決める。
- 公証人に遺言の作成の相談をする。
- 2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人に遺言書を作成してもらう。
まず、自分の財産がどれだけあるのか、財産目録などにまとめましょう。この作業は、他の人に依頼することはできないので自分でやるしかありません。
財産目録を作成したら、誰に相続させたり、遺贈したいのかを決めましょう。
その際に注意することは、法定相続人の遺留分に考慮することです。
特定の法定相続人に財産を集中させる内容の遺言だと、遺産をもらえなかった相続人が相続開始後に遺留分侵害額請求権を行使するリスクがあります。
遺言したい内容をある程度決めたら、公証人に遺言の作成の相談をします。
この際、遺言が無効ではないかや、遺留分を侵害していないかといった法律的な相談をすることも可能です。
公証人が作成する遺言書の原案が固まったら、遺言公正証書の作成日時に2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリットとデメリットを解説します。
まず、公正証書遺言のメリットは次のとおりです。
- 字が書けない場合でも作成できる。
- 遺言の内容が無効になるリスクが少ない。
- 家庭裁判所の検認は必要ない。
- 紛失や改ざんのリスクが少ない。
公正証書遺言は公証人に作成してもらえるので、病気などで自分で文章を書けない場合でも作成することができます。
公正証書遺言のデメリットは次のとおりです。
- 2人以上の証人を用意しなければならない。
- 費用がかかる。
- 時間がかかる。
まず、2人以上の証人を探さなければなりません。見つけられない場合は、公証人が弁護士などの証人を探してくれることもあります。
公正証書遺言の作成の際は、費用が掛かります。
下記のとおり、遺言の目的である財産の価額に対応する形で決められていて、財産が多ければ多いほど、多額の費用がかかります。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
この手数料をベースに様々な加算や手数料がかかります。
また、公正証書遺言の作成を依頼してもすぐに対応してくれるわけではなく、打ち合わせなどが必要になるのが一般的です。
そのため、公証人への依頼や相談から実際に作成されるまで、数週間から数か月の時間がかかります。
弁護士に相談すれば自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらでも問題ない
上記で解説した自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのデメリットは、弁護士に相談した場合はほぼ解消されます。
例えば、自筆証書遺言の作成に先立って弁護士に相談した上、弁護士の監修のもとで、自筆証書遺言を作成すれば、遺言の内容が無効になってしまうリスクは低くなります。
そのため、自筆証書遺言でも、公正証書遺言とそん色ない内容の遺言書を作成することが可能です。
また、公正証書遺言を作成する際も、弁護士がほぼ完璧な原案を作成すれば、公証人はそのまま書くだけになるので、迅速に作成してもらいやすいです。
まとめ
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方や特徴について解説しました。
現在では、自筆証書遺言書保管制度もあるので、両方の遺言の差は少なくなりました。
特に弁護士のアドバイスを受けながら作成した場合ならば、自筆証書遺言でも問題ないことがほとんどです。
遺言書について分からないことや不安な点がある場合は、弁護士にご相談ください。