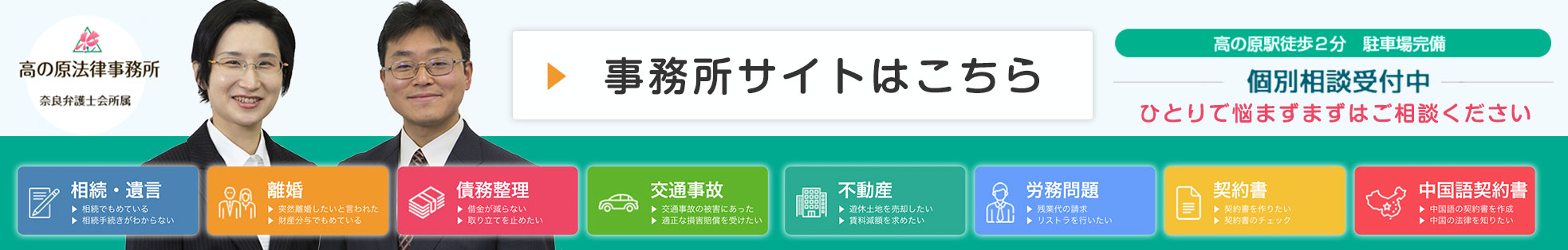コラム
相続財産が不明|亡くなったときにすべき遺産の調査方法を専門家が解説!
身内が亡くなったあと、「相続財産が不明でどうすればよいかわからない」と悩む方は多いです。財産の把握が不十分なまま手続きを進めると、遺産分割のやり直しや申告漏れによる追徴課税が発生するかもしれません。本記事では、相続財産の種類や調査の具体的な進め方、期限、注意点を弁護士がわかりやすく解説します。また、専門家に依頼するメリットについても詳しく紹介します。
身内が亡くなったあと、「どういった財産をもっていたのかわからない」「預金や不動産が見当たらない」と悩む人は少なくありません。
遺産が不明のまま相続を進めると、遺産分割が滞ったり、申告漏れで追徴課税を受けたりするおそれもあります。
この記事では、相続財産の基本から、財産調査の方法や期限、専門家に依頼するメリットまでを詳しく解説します。
調査の流れを理解すれば、相続放棄や遺産分割をスムーズに進める判断が可能です。
限られた時間の中で正確に対応するには、早めの行動が大切になります。
相続財産が不明なときは、まず冷静に全体像を把握し、専門家のサポートを受けながら最適な解決策を選ぶことが重要です。
相続財産とは
相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が生前に所有していたすべての財産を指します。
プラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれる点が重要です。
「相続」とは財産の引き継ぎであると同時に、負債を含めた権利義務の承継でもあります。
プラスの財産(積極財産)には次のようなものがあります。
| 分類 | 主な内容 |
| 不動産 | 土地(宅地・山林・農地など)、建物(自宅・倉庫・店舗など) |
| 金融資産 | 現金、預貯金(普通・定期)、株式、投資信託、公社債など |
| 動産 | 自動車、貴金属、骨董品、家具、家電、事業用資産など |
| その他の権利 | 著作権、特許権、ゴルフ会員権、保険の解約返戻金など |
これらは換金できるため、相続財産として価値をもちます。
遺産分割協議や相続税申告では、こうした財産をすべてリスト化し、評価額を算定することが求められます。
一方で、マイナスの財産も忘れてはいけません。
住宅ローンやカードローンの残債、未払いの税金・公共料金、さらには保証債務なども相続の対象になります。
次のようなものが該当します。
- 借入金(住宅ローン・事業ローン・カード債務など)
- 未払金(水道光熱費・医療費・管理費など)
- 公租公課(未納の所得税・固定資産税など)
相続財産には「資産」と「負債」の両方が含まれます。
どちらが多いかを正確に把握することが、相続の第一歩であり相続財産調査です。
相続財産調査が必要な理由
相続財産が不明な場合は、遺産の分配や税金の計算に大きな支障が生じます。
正確な財産内容を把握することで、将来のトラブルを未然に防げます。
財産調査が必要となる理由は次の3点です。
- 遺産分割協議をするため
- 相続税申告のため
- 相続するか放棄するかを判断するため
それぞれの理由について詳しく説明していきます。
遺産分割協議をするため
相続人間で調整する遺産分割協議には、どの財産を誰が取得するか明らかにする必要があります。
財産調査を怠ると、後から新たな資産が出てきた際に協議をやり直す手間と対立が生じかねません。
たとえば、現金を配分した後に不動産が見つかれば、最初の分け方について協議を再開しなければならなくなります。
調査をもとに正確な一覧を出して共有すれば、協議の再燃を回避できます。
相続税申告のため
相続税の申告を行うには、被相続人の全体的な資産価値を把握しておく必要があります。
漏れがあると、申告後に発覚した資産も含めて過少申告と見なされ、加算税や延滞税が課されるかもしれません。
たとえば、申告時点で相続財産を見積もった後に価値2,000万円の不動産が明らかになると、課税対象が変動し、追加負担が生じます。
正確な調査をもって、申告リスクを軽減できます。
相続するか放棄するかを判断するため
相続を受け入れるか放棄するかを決定するには、プラス財産とマイナス財産の両方を明らかにすることが不可欠です。
調査不十分でマイナス財産を見落とすと、放棄すべき状況を逃す恐れがあります。
たとえば、不動産資産が500万円あっても借金1,000万円が後から出れば、放棄を選ぶべきだったという結論になります。
期限を過ぎた後では負債を引き受けねばなりません。
調査を尽くして判断材料をそろえておけば、誤った選択を回避できます。
相続財産調査の期限
相続が発生したら、財産調査はできるだけ早く始めることが重要です。
相続放棄は「相続開始を知った日から3か月以内」という法定期限があり、この期間内に財産の全体像を把握して判断を行わなければなりません。
3か月という期間は長く見えても、実際には非常に短いです。
なぜなら、財産調査には1〜2か月かかるうえ、相続放棄を選ぶ場合は家庭裁判所への申立書類を整える必要があるからです。
書類の収集や提出準備を含めると、調査は2か月以内に完了していることが望まれます。
効率的に進めるためには、
- 早期に専門家へ相談する
- 銀行・法務局・市役所などへの照会を同時並行で進める
- 遺品の整理を初期段階で行う
といった工夫が欠かせません。
相続財産の調査方法
相続財産を調査するには、財産ごとに行う必要があります。
ここでは下記の5つについて調査方法を解説します。
- 不動産
- 金融資産(預貯金、有価証券)
- 動産
- 権利(使用権・賃料債権・保証債務等)
- 借金(負債)
不動産
不動産は場所や登記情報をおさえないと見落としが起きやすく、名寄帳や固定資産評価証明で所有物件の洗い出しを行います。
続いて法務局で登記事項証明書を取得し、所有権や抵当権の有無を確認します。
所在地の特定
遺品や納税通知書を手がかりに所在地を割り出します。
手がかりがない場合は名寄帳の請求が有効です。
権利関係の確認
登記事項証明書で持分や抵当権を確認します。
登記内容は売却や分割に直結します。
評価と実務手順
相続税申告や売却の際は路線価や公示価格等で評価します。
実勢価格と税務評価は異なる点に留意しましょう。
金融資産①|預貯金
複数の口座や忘れた定期預金が相続財産に含まれていることがあり、まず通帳・カード・郵便物を手がかりに取引金融機関を特定します。
次に各行へ残高証明を請求して死亡日時点の金額を確定します。
手がかりを探す
遺品の通帳やカード、銀行からの封書、ATM利用履歴をチェックします。
スマホやPCに電子明細が残っている場合はログイン情報の確認も有効です。
金融機関への照会
特定した金融機関に残高証明を請求し、必要なら直近の入出金履歴も取得します。
書類と注意点
請求には戸籍や申請者の身分証、印鑑等が必要です。
期限や発行手数料があるため、事前確認を怠らないようにしましょう。
金融資産②|有価証券
株式や投資信託は書面が残らないこともあり、取引報告書や配当通知から証券会社を特定します。
該当先が不明なら証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求して取引口座を確認します。
手がかりの確認
取引報告書、配当書、メール通知、ネット証券の残高画面を探します。
紙がない場合は電子交付の有無も調べます。
残高証明の取得
証券会社に死亡日時点の残高証明を申し込み、評価額を算出します。
非上場株式は発行会社へ照会する必要があります。
海外・暗号資産の扱い
海外口座や暗号資産は別途調査が必要です。
ログイン情報や取引履歴を把握しておきましょう。
動産
動産は現金化しやすい一方で、所在が不明になりやすく、評価のばらつきも大きい財産です。
遺品整理と同時に、価値のある品を丁寧に確認しておくことが大切です。
調査の進め方
車両は車検証から所有者を確認し、査定書で時価を把握します。
貴金属や骨董品は専門業者や鑑定士に査定を依頼し、証明書を保管しましょう。
形見分けをする前に一覧表を作成しておくと、相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。
評価の注意点
市場価格が変動しやすいため、相続税評価では「時価」や「中古市場価格」を基準とします。
高額な動産は、税務署が評価根拠を求める場合もあるため、査定書や取引履歴を残しておくことが望ましいです。
権利(使用権・賃料債権・保証債務等)
契約上の権利や未回収の債権は形が見えにくく、賃貸借契約や貸付契約など契約書類を整理して債権の有無を把握します。
保証債務があれば相続で影響することもあるため、契約相手への照会で条件を確認します。
契約書類の整理
賃貸契約書や貸付証書、会員権の証明書を探し出します。
これらがない場合は取引先への問い合わせが必要です。
債権債務の確認
賃料未収や貸付金の残高を算定し、回収可能性を評価します。
保証債務は引き継ぎの有無を精査します。
相続手続きへの反映
債権がある場合は一覧化して分配の基礎に組み入れます。
法律上の扱いや税務上の評価方法が関係する点は専門家に相談することを推奨します。
借金(負債)
負債の見落としは相続を大きく左右するため、郵便物や督促状から借入先を洗い出し、信用情報機関へ開示請求して金融債務を確認します。
個人間の貸借や非登録の債務は別途文書や関係者からの聴取が必要です。
遺品での手がかり探し
契約書、請求書、ローンの返済明細を探します。
貸金業者からの通知は重要な証拠になります。
信用情報の開示請求
銀行系・クレジット系・消費者金融系の各機関に開示請求を行い、登録されている借入を把握します。
未登録の債務対応
個人間債務や保証債務は相手方や関係書類で確認します。
見落としを防ぐため、生活履歴を辿る作業も必要です。
相続財産調査を専門家に相談すべき理由
相続財産調査は自分たちでも行えますが、親族が亡くなり精神的にもダメージがある中、限られた期間で行うのはなかなか難しいこともあります。
そのため弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談するメリットは下記の3つです。
- 代わりに財産調査と適切な評価をしてもらえる
- 財産調査の時間を短縮できる
- 調停や裁判も対応してもらえる
それぞれ解説します。
代わりに財産調査と適切な評価をしてもらえる
専門家に依頼すれば、金融機関照会や登記情報の取得など手間のかかる調査を代理で行ってくれます。
弁護士は各機関に対する照会や評価計算の経験が豊富で、見落としによる後戻りリスクを減らせます。
遺産調査に加え、権利関係や負債の有無まで整理し、税理面の疑問は税理士と連携して対応可能です。
財産調査の時間を短縮できる
相続の手続きには法律上の期限があるため、限られた時間で進める必要があります。
上述したように、相続放棄や限定承認の申述は「相続開始を知った日から3か月以内」です。
財産調査が遅れると、プラスとマイナスの財産を正確に確認できないまま判断を迫られる事態も起こり得ます。
専門家に依頼すれば、役所・金融機関・証券会社などへの照会や書類請求を並行して進めることが可能です。
個人で行うと数週間かかる手続きを短期間で完了できるケースもあります。
期限内に必要な情報をそろえれば、判断の遅れや手続きミスを防ぎ、安心して次の相続ステップへ進めます。
調停や裁判も対応してもらえる
相続を巡って対立や遺産隠しが疑われる場合、弁護士に依頼すると調停・審判・訴訟まで一貫して任せられます。
弁護士は代理権をもち交渉や法的手続きを代行可能で、調査で得た証拠をもとに主張を組み立てられます。
紛争の可能性があるなら早めに相談することで、手続きの方針や証拠収集方法を弁護士と共有でき、争いの激化をおさえられるでしょう。
まとめ
この記事では、相続財産が不明なときの調査方法や期限、専門家に依頼するメリットまでを詳しく解説してきました。
相続の手続きは感情的にも時間的にも負担が大きく、早めに正確な情報を整理することが重要です。
記事のポイントは以下のとおりです。
- 相続財産にはプラスとマイナスの両方がある
- 相続放棄の判断は3か月以内に行う
- 財産調査は不動産・金融資産・動産など項目ごとに実施
- 専門家へ依頼すれば時間と手間を大幅に削減できる
相続財産の調査は、遺産分割や税申告、放棄の判断を誤らないための第一歩です。
迷ったまま時間が過ぎると、相続放棄の機会を失うおそれもあります。
同じように不安を抱える人も多く、「早く専門家に相談しておけばよかった」という声は少なくありません。
弁護士への相談は初回無料の法律事務所もあります。自分で抱え込まず、早めに専門家を活用して、確実な相続手続きを進めましょう。