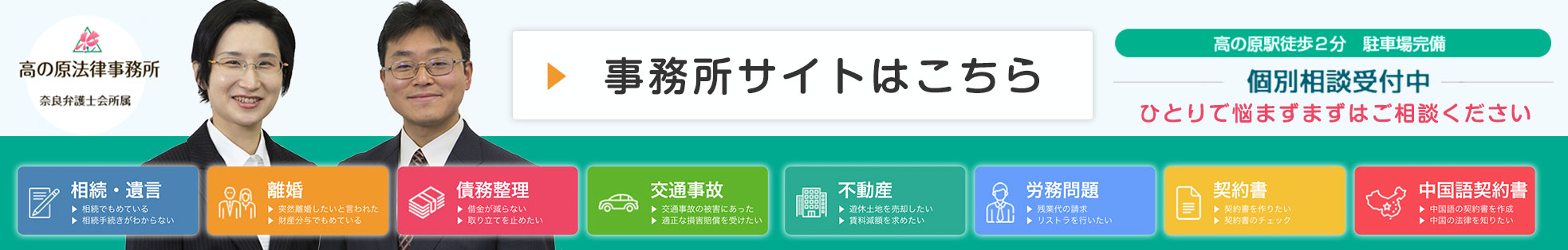コラム
特別受益がある相続で遺留分侵害額を計算、請求する方法を解説
特別受益となる遺贈や生前贈与については持ち戻しの対象となりますし、相続開始前10年までの分は遺留分侵害額請求の対象になります。被相続人死亡時の遺産が少ない場合は、相続開始から1年以内に遺留分侵害額の請求を行いましょう。計算方法も解説します。
特別受益となる生前贈与につき遺留分を主張できるケースをわかりやすく解説
特別受益とは、被相続人から遺産の前渡しを受けた相続人がいる場合に、その分も持ち戻して遺産分割協議を行う制度です。既に遺贈や生前贈与を受けている相続人はその分、遺産相続できる額が少なくなります。
被相続人が特定の相続人に多額の遺贈や生前贈与をしたために死亡時に遺産がほとんどないこともあります。
このようなケースでは、他の相続人は、特別受益となる生前贈与についても、遺留分侵害額請求を行うことができます。
ただし、遺留分侵害額請求の対象とできるのは、10年前までの生前贈与に限られるなど、いくつかの注意点があります。
この記事では、特別受益となる生前贈与につき遺留分を主張できるケースについて、具体例を挙げてわかりやすく解説します。
特別受益とは
特別受益とは、被相続人から生前贈与を受けるなどして、遺産の前渡しを受けていた相続人がいる場合は、その前渡し分も含めて、遺産分割協議を行おうという制度です。
例えば、被相続人Aが生前に6,000万円の遺産を持っており、その相続人は子ども3人のB、C、Dだったとします。
被相続人Aがこのまま亡くなった場合は、B、C、Dが一人当たり、2,000万円ずつ遺産を相続する形になります。
このような形で、B、C、Dが平等に遺産を受け取るなら不満は生じないですし、相続問題も生じにくいでしょう。
では、被相続人Aが亡くなる前にBが生前贈与として2,000万円を受け取っていたらどうでしょうか?
この場合、被相続人Aが亡くなった時点で、遺産は4,000万円に減っています。
この4,000万円をB、C、Dで分け合うと、一人当たり、約1,333万円になります。
生前贈与を受けたBだけは、2,000万円+1,333万円=3,333万円の遺産を得られることになります。C、Dは約1,333万円しかもらえないので不公平です。
このような場合、C、Dに不満が生じないように、Bが生前贈与を受けた2,000万円については、「特別受益」と判断するわけです。
生前贈与分の2,000万円+亡くなった時点の遺産4,000万円=6,000万円を被相続人の遺産総額と計算して、遺産を分け合います。
その結果、相続人Bは、2,000万円の生前贈与を既に受けているので、被相続人が亡くなった時点では遺産はもらえず、C、Dの二人が2,000万円ずつ分け合うという形になります。
特別受益の対象となる贈与とは?
特別受益の対象となる贈与は、上記で解説したように生前贈与分が主です。
具体的には、民法903条に次のように規定されています。
- 遺贈
- 婚姻に伴う生前贈与
- 養子縁組に伴う生前贈与
- 生計の資本のための生前贈与
そして、ポイントは、生前贈与は何年前の生前贈与についてのみ、特別受益の対象になるといった期間が設けられていないことです。
そのため、20年近く前の生前贈与でも特別受益の対象になりえます。
では、具体的にどのようなものが該当するのか確認しましょう。
遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言書で相続人に対して財産を贈与することです。
例えば、6,000万円の遺産を残した被相続人Aが、遺言書で相続人である子ども三人B、C、DのうちのBに、2,000万円を遺贈すると書き残したとします。
すると、B、C、Dが実際に遺産分割できる遺産は残りの4,000万円になります。
これを三人で分け合うと、上記の例で紹介したように不公平になるので、2,000万円の遺贈を受けたBは、それ以上の遺産はもらえないという形になります。
婚姻に伴う生前贈与
婚姻に伴う生前贈与とは、結婚の際の持参金や支度金が代表例です。
また、嫁入り道具として価値のある財産を持たせている場合も、含まれます。
一方、結婚式の挙式費用や結納金、その他のお祝い金などの意味の金銭は、一般的には特別受益の対象にならないと考えられています。
養子縁組に伴う生前贈与
養子縁組に伴う生前贈与とは、持参金が代表例です。
普通養子縁組の場合は、養子となっても実親との関係は切れないため、実親が亡くなった際に相続人になることができます。
この場合に、生前贈与分が特別受益に当たる可能性があります。
生計の資本のための生前贈与
生計の資本のための生前贈与とは、親が子どもの生活資金を援助することで、代表的なのは、子どもが住居(土地、建物)を購入する際の資金を援助することです。
その他、相続税対策として生前贈与が行われていた場合も含まれます。
なお、大学の学費などは、一般的な四年制大学までであれば、特別受益に含まれないと考えられています。
ただ、私立の医学部や留学費用など、特別に学費がかかるケースでは、特別受益と判断します。
特別受益の対象となるのは相続人のみ
特別受益の対象となるのは相続人だけです。
例えば、被相続人Aが6,000万円の遺産を残して亡くなり、法定相続人が子ども三人のB、C、Dだったとします。
そして、被相続人は遺産のうち、3,000万円を第三者である慈善団体に遺贈しました。
この場合は、B、C、Dは残りの3,000万円を等しく分けあうしかなく、第三者である慈善団体に対して、特別受益の主張はできません。
特別受益の持ち戻し免除とは?
特別受益に当たる生前贈与は、何年前になされたものでも、相続時に財産に加えるのが原則です。これを「持ち戻し」と言います。
ただ、被相続人が遺言書により、「持ち戻し」を免除することもできます。
例えば、6,000万円の遺産を有する被相続人Aが法定相続人である子ども三人のB、C、Dのうち、Bに、3,000万円の生前贈与をしたとします。
そして、Aが遺言書に、「遺言者Aは令和何年何月何日にBに対して、金3,000万円を贈与したが、民法第903条第1項に規定する相続財産の算定にあたっては、当該贈与の価額を加えないものとする」と書き残しました。
この場合は、Bに生前贈与された3,000万円については、特別受益として持ち戻ししなくてよいことになります。
そのため、被相続人Aが亡くなった時点で残っていた遺産3,000万円のみが遺産分割の対象になります。
法定相続分で分け合うなら、B、C、Dはそれぞれ、1,000万円ずつ相続することになり、Bは3,000万円+1,000万円=4,000万円を受け取れることになります。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分の割合は、原則として、法定相続分の2分の1です。
法定相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1になります。
夫が亡くなり、その法定相続人が妻(配偶者)と2人の子どもだったとします。
この場合の法定相続分の割合は次のようになります。
子ども(2名)4分の1ずつ
そして、それぞれの遺留分の割合は法定相続分の2分の1になります。
具体的には次のとおりです。
子ども(2名)8分の1ずつ
例えば、この夫が8,000万円の遺産を残していたとすれば、法定相続分で分けた場合は次のようになります。
子ども(2名)2,000万円ずつ
そして、この夫が8,000万円の遺産を第三者である慈善団体に全額寄付してしまったとします。
この場合でも、妻(配偶者)と子どもたちは、最低限の取り分である遺留分を主張することができます。
具体的な金額は次のようになります。
子ども(2名)1,000万円ずつ
遺留分の主張方法
遺留分を主張する際には、遺留分を侵害する遺贈を受けた人(受遺者又は受贈者)に対して、遺留分侵害額の請求を行う形になります。
上記の事例でいえば、8,000万円の遺産の寄付を受けた慈善団体に対して、妻や子どもがそれぞれの遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。
受遺者又は受贈者への遺留分侵害額請求は、調停や裁判による必要はなく、相手との話し合いや直接交渉による形でも構いません。
遺留分侵害額請求権の行使期間(時効)
遺留分侵害額請求権の行使期間は短いです。
遺留分を有している人(遺留分権利者)が、
- 相続が開始したこと
- 遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと
の2点を知った時から、1年以内に行使しなければ時効になります。
また、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から10年で消滅時効にかかり、以後は権利行使ができなくなります。
行使期間内に権利行使したことの証拠を残すために、内容証明郵便なども活用しましょう。
遺留分侵害額請求の対象となる贈与とは?
遺留分侵害額請求の対象となる贈与は、遺贈はもちろん、生前贈与の分も含みます。
そして、特別受益と異なり、対象となる贈与の期間が設けられていることがポイントです。
具体的には、
- 相続人以外の人への贈与については、相続開始前の1年間になされたもの
- 相続人への贈与については、相続開始前の10年間になされたもの
この2つが、それぞれ、遺留分侵害額請求の対象になります。
なお、相続人への贈与については、「婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与の価額に限る」とされており、特別受益と範囲は同じです。
特別受益と遺留分の関係
特別受益は、相続人への遺贈や生前贈与のみが対象ですが、生前贈与の期間に限定はありません。
遺留分侵害額請求の対象は、相続人だけでなく、第三者への遺贈や生前贈与も含みます。ただ、対象となる期間は限定されています。
特別受益については、相続開始前の10年間になされたものだけが遺留分侵害額請求の対象になります。
特別受益と遺留分の関係について具体的な事例で解説
Aさんは亡くなる前に6,000万円の財産がありました。Aさんには三人の子どもB、C、Dがいます。
Aさんが亡くなる直前まで6,000万円を有しており、これを法定相続分で分けた場合は、B、C、Dの相続分はそれぞれ、2,000万円ずつになります。
この事例をベースに様々なケースを想定して見ていきましょう。
Aさんが亡くなる9年前にBさんに対して5,100万円の生前贈与をした場合
Aさんが亡くなった時点で残された遺産は900万円しかありません。
B、C、Dの三人で300万円ずつ分けると、Bが5,100万円+300万円=5,400万円相続したことになり不公平です。
この場合、C、Dは、Bの特別受益を主張して、Bが生前贈与を受けた5,100万円も遺産に持ち戻して計算すべきと主張できます。
Bは既にもらいすぎですから、亡くなった時点での法定相続分はありません。
C、Dがそれぞれ、450万円ずつ相続できることになります。
ただ、それでも、5,100万円もの生前贈与を既に受けたBと450万円しかもらえないC、Dの差は大きいです。
そこで、C、Dは、遺留分が侵害されているとの主張を検討します。
遺留分の計算に当たっては、特別受益に相当する生前贈与分も10年前の分までなら含めることができます。
Bさんは、Aさんが亡くなる9年前に生前贈与を受けていますから、この分も遺留分を算定するための財産の価額に加えることができます。
つまり、5,100万円+900万円=6,000万円を基に、C、Dの遺留分を計算できるわけです。
C、Dの遺留分は、法定相続分の2分の1なので、3分の1×2分の1=6分の1です。
6,000万円の遺産総額に当てはめると、それぞれの遺留分は、1,000万円になります。
C、Dは、Aさんが亡くなった時点で、450万円ずつしか相続できません。
よって、C、Dは、遺留分の1,000万円から450万円を差し引いた「550万円」について、それぞれがBに対して、遺留分侵害額請求権を行使できることになります。
Aさんが亡くなる9年前にBさんに対して5,100万円を生前贈与し、持ち戻し免除の遺言書を残していた場合
このケースは、持ち戻し免除した特別受益の分は、遺留分侵害額請求の対象にならないのかという話です。
この点について最高裁は、持ち戻し免除した特別受益の分についても遺留分侵害額請求ができるとの判断を示しました(最判平成24年1月26日 集民 第239号635頁)。
よって、持ち戻し免除の遺言書が残っていたとしても、上記と同様に計算してよいため、C、Dは、遺留分の1,000万円から450万円を差し引いた「550万円」について、それぞれがBに対して、遺留分侵害額請求権を行使できます。
Aさんが亡くなる15年前にBさんに対して5,100万円の生前贈与をした場合
この場合も、Aさんが亡くなった時点で残された遺産は900万円しかありません。
Bさんへの5,100万円の生前贈与はもちろん特別受益に当たります。
そのため、法定相続分で分け合う場合は、C、Dのみが450万円ずつ相続できることになります。
そして、特別受益については、相続開始前の10年間になされたものだけが遺留分侵害額請求の対象になります。
そのため、15年前の生前贈与については、残念ながら、遺留分を算定するための財産の価額に加えることができません。
よって、C、Dはそれぞれ450万円しか相続できないということです。
まとめ
今回は、特別受益及び遺留分がどのような関係にあるのか解説しました。
特別受益は、被相続人から生前贈与を受けていたり、遺贈を受けた相続人がいる場合に、その生前贈与や遺贈の価額を持ち戻して、相続財産の計算をする制度です。
生前贈与や遺贈を受けた相続人は、被相続人死亡時の遺産からの取り分が少なくなります。
それでも生前贈与が多額である場合は、10年前までの生前贈与分について、遺留分侵害額請求の対象とすることもできます。
このような場合、他の相続人は、多額の生前贈与を受けた相続人を相手に、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
特別受益と遺留分の関係はややこしい話なので、理解できない方もいらっしゃるかと思います。
もしも、この辺りの話で相続トラブルに発展している場合は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼いただければ、特別受益と遺留分の正確な計算を行うことができます。