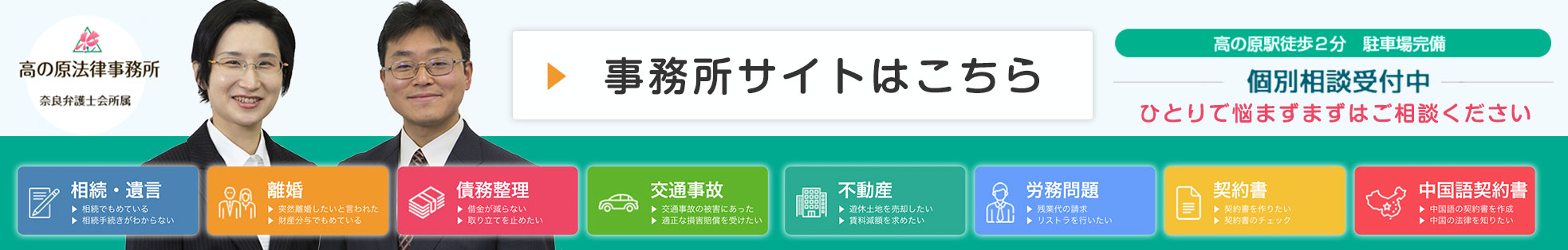コラム
遺言能力とは?判断のポイントや疑問の残る遺言書への対応について弁護士が解説!
遺言書においては「遺言能力」を巡って相続人や親族間で争いになることは少なくありません。
この記事では、遺言能力の定義や法律上の要件、判断のポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
遺言能力は年齢・診断結果・遺言内容などから総合的に判断されます。
トラブルを避けて相続するには、正しい知識と証拠の備えが不可欠です。
遺言能力とは?判断のポイントや疑問の残る遺言書への対応について弁護士が解説!
財産について、自分がなくなった後の遺産分割のことを考え、遺言書を残す人は多いです。
しかし、遺言者(遺言を書いた人)である被相続人に「遺言能力がない」と判断された場合、どれほど丁寧に書いた遺言書でも効力をもたない可能性があります。
また遺言書の内容に納得できない人は、そもそも遺言書が正しい判断のもと書かれたものかどうか疑問に思う人もいるでしょう。
この記事では、遺言能力の基本的な定義から法律上における要件について解説します。
また、実際にどのような点で遺言能力の有無が判断されるのかも詳しく紹介します。
効力のある遺言をどのように残せるかや無効になりやすい遺言が明確になり、トラブルを避ける準備ができるでしょう。
遺言能力とは
遺言能力とは、自分の判断で有効な遺言書を作成する力があることを指します。
遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の形式があり、どの形式であっても遺言能力が欠けていれば無効です。
遺言書を残すときは、遺言能力を証明する準備も同時に進めることで後のトラブルを防げます。
遺言能力があったかどうか、最終的に判断するのは裁判所です。
たとえば、相続人同士で「この遺言は無効だ!」という訴訟になった場合、家庭裁判所や民事裁判所が、遺言作成当時に本人に「遺言能力(意思能力)」があったかを証拠に基づいて判断していきます。
遺言能力がないと「遺言無効」となる
上述の通り、遺言能力が認められない場合、作成された遺言書は無効と判断されます。
いくら書式や手続が正しくても、意思能力がなかったと証明されれば効力をもちません。
たとえば、遺言作成時に認知症が進行していた場合、その判断力に疑いが生じます。
このケースでは相続人が異議を唱え、裁判で無効とされることもあります。
遺言を確実に残すには、能力があったことの証拠を整えておくことが大切です。
遺言能力の要件
民法(961条・963条)においては、遺言作成に関する要件が定められています。
具体的な要件は次の2つです。
- 満15歳以上
- 意思能力
これらの要件を満たしていなければ、たとえ法律にしたがって作成された遺言書であっても効力をもちません。
それぞれの要件について解説します。
満15歳以上
法律では、遺言を行うには満15歳に達していることが必要です。
この年齢に達していれば、未成年であっても親の許可は不要で、自ら遺言を残せます。
一方で、15歳未満で作成された遺言は、たとえ内容がしっかりしていても効力が認められません。
また、遺言は本人自ら行う必要があり、代理人を立てることはできません。
意思能力
遺言を書くには、自身の行動の意味や結果を理解する認知的な能力が求められます。
これを意思能力と呼びます。
たとえば、認知症の症状が進んでいた場合、その判断力が問われるかもしれません。
意思能力がないと判断されれば、その遺言は無効とされることもあるため、医師の診断などが重要になります。
遺言時の言動や病歴、診断内容などが能力の有無を見極める根拠となってきます。
遺言能力を判断するポイント
遺言能力の要件である意思能力については複数の判断材料から総合的に判断されます。
判断のポイントは次のような点です。
- 年齢
- 遺言者が受けた診断
- 長谷川式スケールのスコア
- 要介護認定の資料
- 遺言の内容
- 遺言作成した理由
- 受遺者との人間関係
それぞれのポイントについて説明していきます。
年齢
高齢になると記憶力や判断力が低下し、遺言能力がないと判断されやすくなります。
しかし、年齢だけで遺言能力が否定されるわけではありません。
たとえば、90歳を超えていても、日常生活を自立して送っている方も多いです。
遺言能力の有無は、年齢だけでなく、健康状態や生活状況などを総合的に判断する必要があります。
そのため、年齢は一つの要素として考慮されますが、決定的な要因ではありません。
遺言者が受けた診断
遺言能力の判断には、医師の診断結果も重要です。
とくに、認知症や精神疾患の有無、症状の程度などが評価対象とされます。
診断書や医療記録は、遺言作成時の判断能力を示す客観的な証拠です。
また、遺言作成前後の医師との面談内容や治療経過も、能力の有無を判断する材料です。
長谷川式スケールのスコア
長谷川式認知症スケール(HDS-R)は、認知機能を評価するための検査です。
このスコアは、遺言者の判断能力を客観的に示す指標として利用されます。
高得点であれば、認知機能が保たれている可能性は高く、遺言能力があると判断されやすいです。
ただし、スコアだけで能力の有無を決定することはできません。
他の要素と合わせて総合的に判断することが求められます。
要介護認定の資料
要介護認定を受けている場合はその資料も、遺言能力の判断の参考になる情報です。
とくに、認知機能や日常生活の自立度に関する評価が含まれているため、遺言者の判断能力を推測する手がかりとなります。
ただし、要介護度が高いからといって、必ずしも遺言能力がないとは限りません。
身体的な介助が必要でも、判断能力は保たれている場合もあります。
遺言の内容
遺言書の内容としてどのような記述がされているかも大きな判断材料になります。
たとえば、遺言の内容がシンプルで理解しやすい場合、多少判断力が衰えていたとしても有効とされやすくなります。
預金の一部を子どもに渡すような内容であれば、複雑な判断は不要ですよね。
一方で、不動産や株式を細かく分けるような難しい内容になると、作成時の判断能力がより厳しく問われるでしょう。
遺言作成した理由
意外かもしれませんが、遺言を作成した理由も遺言能力の有無を判断する重要な要素です。
家族間のトラブルを避けるためや、特定の相続人に感謝の気持ちを伝えるためなど、合理的な理由がある場合、判断能力があると評価されやすくなります。
一方で、内容から突発的な感情や外部からの影響によって作成された可能性がある場合、能力の有無が疑問視されやすいです。
受遺者との人間関係
遺言者と受遺者との関係性も、遺言能力の判断に影響を与えます。
長年にわたる親密な関係がある場合、遺産を譲る動機が明確であり、判断能力があると認められやすいです。
反対に、ほとんど交流がなかった人物に多額の遺産を譲る内容であれば、その動機や判断能力に疑問が生じやすいでしょう。
人間関係の深さや継続性も、遺言の合理性を裏付ける要素です。
遺言能力を巡る争いの予防方法
遺言に関する争いは、相続人間での感情的な対立を深める原因となります。
遺言能力の有無が疑問視される場合、遺言自体の効力を巡って法的トラブルが起こりやすいです。
そのような事態を避けるには、遺言作成時に能力が確かであることを客観的に示しておく工夫が求められます。
方法としては次の2つがあります。
- 公正証書遺言の作成
- 医師の診察を受ける
それぞれ解説します。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成される遺言書です。
自筆証書遺言と異なり、公証人が遺言者の受け答えや様子を直接確認するため、作成時点で一定の判断力があったことを第三者が記録します。
このような手続を経て作成された遺言書は、遺言能力を否定する側が証明を求められる構図になりやすく、有効性が高く評価されます。
将来の争いを未然に防ぐ手段として、有力な方法といえるでしょう。
医師の診察を受ける
遺言作成の直前や直後に医師の診察を受けておくことも、有効な対策です。
診察によって認知機能が保たれていることを確認できれば、その記録は遺言能力を裏付ける材料となります。
診断書の取得やカルテのコピーを保管しておけば、後日の証拠として活用できるでしょう。
また、年齢が若いうちに遺言を残しておけば、判断能力に関する疑い自体が少なくなります。
遺言者の遺言能力に疑問がある場合
遺言能力を巡る疑問があるとき、どう動けばよいか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
遺言書の内容に納得できない場合や、遺言者の遺言能力に疑問がある場合は次のような順序で遺言の内容を無効もしくは変更できるかもしれません。
1. 相続人・受遺者と話し合い
2. 遺言無効調停
3. 遺言無効確認訴訟
それぞれ解説します。
相続人・受遺者と話し合い
遺言の内容や遺言者の判断力に不安がある場合は、まず相続人や受遺者と率直に話し合いましょう。
話し合いによって全員の合意が得られれば、遺言の内容とは異なる方法で遺産分割が可能です。
遺言執行者が指定されているケースでは、その人の同意も必要です。
話し合いの段階で解決できれば、調停や裁判にならずに済みます。
遺言無効調停
話し合いで合意に至らなかった場合、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てられます。
この調停は、中立的な立場の調停委員が関わり、公正な話し合いを支援する制度です。
申立は相手方の住所地の家庭裁判所を基本としますが、合意によって別の裁判所に申し立てることもできます。
調停は比較的話し合いによる解決を目指す手段です。
遺言無効確認訴訟
調停でも解決できなかった場合には、「遺言無効確認訴訟」の提起となります。
これは裁判所で法的に遺言の有効・無効を判断してもらう手続で、遺言の有効性が裁判官によって決まります。
万が一訴えが認められない場合でも、遺留分の請求など別の法的手段をとることが可能です。
遺言能力を巡る件は弁護士に相談を
遺言能力を巡る争いや手続きには、法律の専門的な知識が必要なため、専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。
具体的なメリットは多々ありますが、主な点は次の3つです。
- 遺言能力について証拠収集と整理ができる
- 不利な遺言内容を無効にできる
- 遺言者の真意を守れる
それぞれのメリットについて解説します。
遺言能力について証拠収集と整理ができる
遺言能力の有無を争う際には、的確な証拠を用意することが必要です。
弁護士に依頼すれば、医師の診断書や介護記録、本人の言動に関する資料などを適切に集めるサポートを受けられます。
また、集めた証拠をどのように主張するか整理し、訴訟に備える体制も整えられます。
証拠の収集と活用は専門的な判断が必要なため、弁護士の関与が有効です。
不利な遺言内容を無効にできる
遺言内容が偏っていたり、遺留分が侵害されていたりするなど、法的に問題がある遺言は無効を主張することが可能です。
「遺産が一部の人に集中している」「本人の判断力に疑問がある」といった事情があれば、遺言の有効性を争えます。
弁護士は証拠をもとに主張を組み立て、裁判所に納得してもらえる形で訴訟に臨める力をもっています。
個人での対応が難しい場面でも、専門家のサポートがあれば望む結果につながりやすいでしょう。
遺言者の真意を守れる
遺言者が伝えたかった思いを尊重するには、法的に正しい形で遺言が残されているか確認が必要です。
もし第三者の影響で内容が歪められていた場合には、その点を明らかにしなければなりません。
弁護士に相談すれば、当時の状況を調査し、遺言者の意思がどこにあったのかを明らかにできます。
正しい形で遺言者の意思を反映させるための支援を受けられます。
まとめ
この記事では、遺言能力の法律上の要件や、実際にどのような点で能力の有無が判断されるのかなどを解説してきました。
遺言能力を巡る不安や争いを避けるには、以下のポイントが重要です。
- 遺言能力には「満15歳以上」「意思能力」の2要件がある
- 遺言能力は年齢・診断結果・遺言内容などから総合的に判断される
- 医師の診断や公正証書遺言で遺言能力は客観的に証明できる
- 遺言能力に疑いがあるときは、話し合い→調停→訴訟の順で対応する
- 弁護士に依頼すれば証拠収集や裁判対応も安心
遺言書は形式だけでなく、遺言者の判断力が問われる書類です。
正しく作成しておくことで、相続人同士のトラブルも未然に防げます。
迷った際は専門家である弁護士に相談してみましょう。
初回の相談についは、費用が無料の法律事務所もありますよ。