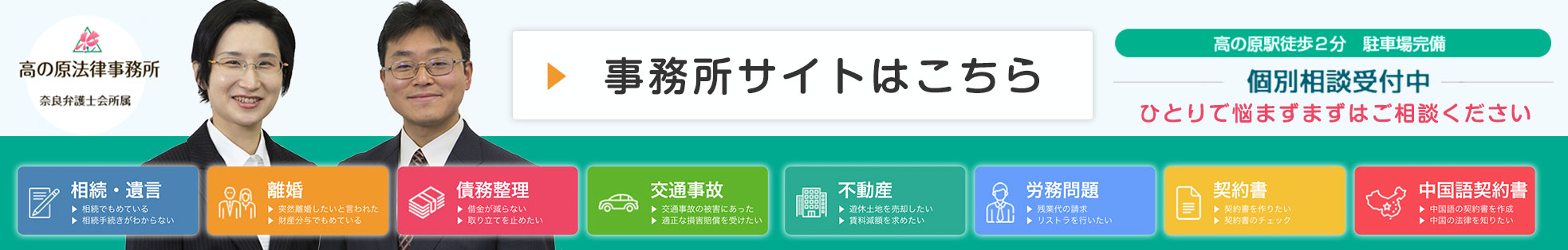コラム
相続放棄したら借金は誰が払うのか? 相続トラブル回避のポイントを解説
親が借金を残して亡くなった場合は相続放棄により借金の相続を回避できます。この場合でも借金はなくなるわけではなく他の相続人が代わりに借金を相続してしまうため、親族間のトラブルになってしまうことがあります。相続放棄した場合の注意点や相続放棄後の遺産の管理義務などについて解説します。
相続放棄すると借金は誰が払うのか? 相続放棄時の注意点を解説
被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合は、相続を承認するとその借金も相続してしまいます。この場合は、相続放棄の手続きを行うことで、借金を相続する事態を防ぐことができます。
では、相続放棄した場合、借金は誰が払うのでしょうか? 結論から言うと、他の相続人が代わりに借金を相続してしまい、支払い義務を負う可能性があります。
そのため、相続放棄した時は、他の相続人にも事情を説明して相続放棄するよう促すことが大切です。
また、相続放棄した場合でも、法定単純承認に該当しないように相続財産の扱いには注意が必要です。
相続放棄を行うと借金は誰が払うのか? 相続放棄時の注意点は何か? について解説します。
借金などの負債も相続の対象になる
被相続人が多額の借金などを残して亡くなった場合は、その借金は相続することで相続人が承継します。
相続というと、親が残した土地や建物、動産、銀行預金や株式といったプラスの財産を承継するイメージが強いですが、借金などのマイナスの遺産も相続してしまいます。
そのため、遺産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産を合わせて計算した結果、マイナスの遺産の方が多い場合は、借金を相続する形になるので相続放棄を検討すべきことになります。
借金などの負債は原則として相続人が等しい割合で相続する
土地や建物、動産、銀行預金や株式といったプラスの財産は、相続人同士が遺産分割協議により、誰が相続するか自由に決めることができます。
一方、借金などのマイナスの遺産は、原則として、法定相続分に応じて相続人全員が相続します。
連帯債務や不可分債務の場合は、各相続人が債務の全部について弁済の責任を負うことになります。
相続人同士で、被相続人が残していった借金は、例えば、長男がすべて引き受けると決めたとしても、それだけでは、債権者に対して主張することができません。
被相続人の債務を特定の相続人のみに承継させるには、その債権者に債務の承継を承認してもらう必要があります(民法902条の2但書等)。
そのため、遺産分割協議の結果、プラスの財産を相続しない方は、相続放棄をしておかないと、借金などのマイナスの遺産だけを相続してしまう可能性もあるので注意しましょう。
借金等の負債の相続を避けたい時は相続放棄する
被相続人が残した借金等の負債を支払わされる事態を避けるためには、相続放棄の手続きを行うのが最も確実な方法です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で申述を行うことによって、行います。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、相続放棄の申述書と添付書類を提出します。
相続放棄に必要な費用は、収入印紙800円分や戸籍謄本等の取得費用といったものだけです。
3か月以内という期限をしっかり遵守してください。
なお、相続放棄が受理されても、その旨が債権者等に通知されるわけではありません。
そのため、債権者から借金の支払いの催促を受けた際は、相続放棄が受理された証明書を家庭裁判所に発行してもらい、それを債権者に示すなどして、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたことを伝える必要があります。
相続放棄した場合、被相続人の借金を誰が払うのか?
相続放棄した場合、他の相続人が被相続人の借金を承継して支払うことになります。
まず、第一には同順位の相続人が承継し、同順位の相続人が全員、相続放棄を行う場合は、次順位の相続人が承継します。次順位の相続人も全員が相続放棄すれば、第三順位の相続人が承継することになります。
具体例で見ていきましょう。
親子間の相続
夫Aさんが膨大な借金を残して亡くなったとします。
Aさんには妻と三人の子どもがいます。子どもの一人Bさんは結婚していて、Aさんの孫がいるとします。
まず、この事例では法定相続分は、妻が6分の3、Bさんを含む三人の子どもたちは6分の1です。
Aさんが残した膨大な借金もこの割合で承継するのが原則です。
この事例で、Bさんが相続放棄を行ったとします。
この場合、Aさんが残した膨大な借金は、妻が4分の2、Bさん以外の二人の子どもがそれぞれ4分の1ずつ承継する形になります。
ところで、Bさんには孫がいます。
遺産相続では、代襲相続と言い、上の世代が相続人の権利を失った時は、その下の世代の人が代襲して相続できるという制度があります(民法887条2項)。
ただ、相続放棄については、代襲相続は生じません。つまり、Bさんが相続放棄しても孫が代わりにAさんの借金を相続する事態にはなりません。
直系尊属の相続
上記の設定の続きです。
Aさんの三人の子どもの全員が、相続放棄したとします。
この場合、Aさんには直系卑属がいなかったのと同じ状態になりますから、次にAさんが残した膨大な借金を引き継ぐのは、Aさんの両親です。
Aさんの妻が相続放棄していない場合ですと、法定相続分は妻が6分の4、Aさんの両親はそれぞれ、6分の1ずつなので、Aさんの借金も同様の割合で承継してしまいます。
妻も相続放棄を行っている場合は、Aさんの両親が借金をすべて承継してしまうことになります。
そのため、Aさんの妻と子どもたち全員が相続放棄した場合は、Aさんの両親にも連絡して、相続放棄するように促さなければ、Aさんの両親に借金を押し付ける形になってしまうので注意が必要です。
兄弟姉妹の相続
上記の設定の続きです。
Aさんが亡くなった時点で、Aさんの両親も既に他界していたとします。そして、Aさんの三人の子どもの全員が、相続放棄したとします。この場合は、Aさんの兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、Aさんの妹Cさんが一人いたとします。
Aさんの妻が相続放棄していない場合ですと、法定相続分は妻が4分の3、Cさんが4分の1なので、Aさんの借金も同様の割合で承継してしまいます。
妻も相続放棄を行っている場合は、Cさんが借金をすべて承継してしまうことになります。
やはり、Aさんの妻と子どもたちの全員が相続放棄した場合は、Cさんにも連絡して、相続放棄するように促さなければ、Cさんに借金を押し付ける形になってします。
なお、Aさんが亡くなった時点で、Cさんが他界している場合は、Cさんの子ども、つまり、Aさんの甥、姪が代襲相続できる立場になります。
甥、姪も、借金を承継してしまうため、甥、姪に連絡して相続放棄するように促す必要があります。
法定相続人の全員が相続放棄した後
法定相続人の全員が相続放棄した後は、誰もAさんの借金を承継しないことになります。
この場合は、債権者などの関係者がAさんの相続財産清算人の選任を申し立てた上で、プラスの相続財産の範囲で、借金の回収を試みます。
仮にプラスの財産が余ったとしても、残りの財産はすべて国庫に帰属します。
例外的に、特別縁故者と認められた人のみが残りの財産を承継できることがあります。
相続放棄する際の注意点
相続放棄の手続きを行う際に注意すべきことをまとめておきます。
他の相続人が借金等の負債を負うことになる
相続放棄をすることは、相続人に認められた権利なので、各相続人が自由に行使することができます。
ただ、相続放棄を行う場合は、上記の解説で紹介したとおり、借金などの負債を他の法定相続人が相続してしまうので注意しましょう。
妻と子どもの他、祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹、甥、姪などがいる場合は、故人に借金があるといった事情を説明したうえで、相続放棄を行うように促すことが大切です。
親戚付き合いがなく、疎遠になっている場合でも、そのことだけでも伝えておかないと後で大変なトラブルに発展してしまいます。
法定単純承認に注意する
相続人になったのに3か月間、何もしないでいる場合などは、法定単純承認といい、自動的に相続を承認したことになるので注意しましょう。
また、相続財産に手を付けた場合も同様です。
具体的には次のような行為をした場合は法定単純承認になります(民法921条)。
- 相続財産の全部又は一部を処分した場合。
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合。
- 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。
債権者から借金の返済を催促されても支払いには応じない
被相続人が借金を残していた場合は、被相続人が亡くなった後で、債権者から相続人に借金の返済の催促が行くこともあります。相続放棄する前だけでなく、相続放棄した後でも、催促が来ることがあります。
相続放棄を検討しているのなら、債権者から借金の返済を求められても返済に応じてはいけません。
被相続人の遺産から借金を返済してしまうと、上記で紹介した「法定単純承認」に該当してしまいます。
相続人が自分のお金で返済することは問題ないですが、被相続人の遺産から返済したと疑われてしまう可能性があります。
そのため、債権者から借金の返済を催促されても一切応じない姿勢を貫くことが大切です。
なお、相続放棄した後であれば、相続放棄が受理された証明書を家庭裁判所に発行してもらい、それを債権者に示せば、大抵の場合、借金の取り立ては止みます。
相続放棄後も遺産を管理する義務がある
相続放棄した後は、相続財産に一切関わらなくてよいわけではありません。
相続放棄した場合でも、その時点で占有している相続財産は、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、管理する義務が生じます(民法940条)。
なお、管理するのが面倒だからと言って勝手に売却したり、処分してはいけません。相続財産に手を付けると相続放棄した後でも、法定単純承認に該当してしまうので注意が必要です。
相続放棄の撤回はできないので慎重に判断する
借金などの負債しかないケースではためらいなく相続放棄すべきですが、プラスの遺産がある場合は、相続放棄をすべきなのか慎重に検討しましょう。
一旦、相続放棄を行うと、原則として後で撤回することはできません。
銀行の預貯金や不動産などのプラスの資産と借金などの負債を突き合わせて計算した結果、実際には、プラスの資産の方が多いかもしれません。
また、借金などの負債にしても、債務整理を行えば、減らせる可能性があります。債務整理の結果、プラスの遺産が残る可能性もあるわけです。
プラスの財産が残るのかどうか微妙な場合は、限定承認という相続方法を選択することもできます。
限定承認とは、被相続人が残した借金などの負債は被相続人のプラスの財産の範囲でのみ弁済する旨を留保して相続するというものです。
相続人の全員が共同で家庭裁判所に申述することにより限定承認が可能になります。
相続放棄に関して押さえておきたいこと
相続放棄に関してよくある疑問点をまとめておきます。
相続放棄しても受け取れる財産はある
相続放棄した後でも、受け取れる財産があります。
例えば、被相続人が掛けていた生命保険金は、相続放棄するかどうかに関わらず、受取人となっている方が受け取ることが可能です。
受取人が相続人で、相続放棄を行っていたとしても問題ありません。
その他、次のようなものは相続放棄した後でも受け取ることが可能です。
- 死亡退職金
- 遺族年金
- 未支給年金
- 葬祭費、埋葬料
- 香典
- 祭祀財産
生活保護を受けていると相続放棄できない?
相続人が生活保護を受けている場合は、原則として相続放棄を行うことはできません。
相続によって相続財産を承継し、生活保護が必要な状態から抜け出せるように努力することが求められているからです。
もしも、プラスの資産があるのに相続放棄を行った場合は、生活保護の支給停止処分等を受けてしまう恐れがあるので注意してください。
なお、借金などの負債が多い場合は、相続放棄を行うことも可能です。
被相続人の借金を連帯保証している場合でも相続放棄できるのか?
相続人が被相続人の借金を連帯保証している場合でも相続放棄することは可能です。
例えば、亡くなった親の借金について子どもが連帯保証していた場合です。
ただ、連帯保証した分の借金は、相続放棄したとしても、連帯保証人として弁済しなければならないので注意しましょう。
借金があることを知らなかった場合、後で相続放棄できるのか?
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内しか認められていません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、一般的には被相続人が亡くなった時点です。
多くの場合、被相続人が亡くなった日から3ヶ月経過すると、相続放棄をすることができません。
では、被相続人が亡くなった日から3ヶ月経過した後で、借金が発覚した場合は、相続放棄することができるのでしょうか?
この点、相続人がプラスの遺産があることは認識していたもののその価値がほとんどない一方で、借金などの負債はまったく存在しないと信じ、かつ、そう信じることにつき、正当な理由がある場合ならば、借金などの負債が発覚した時点から3ヶ月以内なら相続放棄が可能とする裁判例があります(東京高決平成19年8月10日)。
こうした事情により相続放棄を行うには、相続放棄の申述を行う際に、家庭裁判所に対して説得力のある説明を行う必要があります。
ご自身で説明することが難しいと感じられた時は、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
まとめ
相続放棄を行った場合は、借金などの負債は他の相続人が承継することになります。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、ご自身については、被相続人が残した借金の返済を免れることができますが、あなたの代わりに相続人になった方に借金の催促が行くことがあるため、法定相続人に当たる方には、事情を説明して相続放棄するように促すことが大切です。
また、相続放棄した場合でも、遺産の管理などについて、様々な注意点があります。
相続放棄に関して分からないことやトラブルを抱えそうなときは、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。